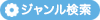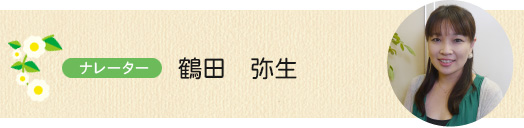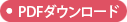北九州市人権推進センターがお送りする「明日への伝言板」です。
今日は、北九州市が平成24年度に募集した
人権作文の入選作品の中にあったお話を紹介します。
三十年ほど前、教員として勤務していた幼稚園に、
知的障害のあるAくんが在籍していた。
Aくんは、自力歩行はできるが、言葉はなく、
口を開けていつもニコニコしていた。
子どもたちは、Aくんが何かできれば手をたたいて喜び、
できないことはこぞって手伝い、
彼と共に過ごす中で心も大きく育っていった。
ある日、Aくんの担任からこんな話を聞かされた。
生活発表会でAくんの鍵盤(けんばん)ハーモニカに細工をして、
音が出ないようにするのだという。
間違った音を鳴らされると曲が台無しだから、と。
生活発表会は園の一大イベントで、保護者の期待も高い。
合同演奏を成功させたい気持ちは分かるが、あんまりだ。
でも、私はどうすればよいか分からず、意見する勇気もなかった。
合同演奏は無事に披露され、大きな拍手を浴びた。
もしかしたらAくんは事実を知っていて、
私たちの心の未熟さを黙って受け入れてくれたのではないか…。
そう思ったのは、その後、私自身が知的障害のある娘の母となったからだ。
娘を育てた時代は、社会も教育現場も、
少しずつ障害者の人権が重視されるようになっていた。
娘が小学六年生のとき、運動会で鼓笛(こてき)パレードがあった。
娘は、みんなと同じように歩きながら鍵盤ハーモニカを吹くのは難しい。
だからといって、障害を理由に娘がみんなの鼓笛パレードを
台無しにするようなことがあってはならない。
そこで私は先生に相談し、娘にも吹けるようにオリジナルの譜面を作り直し、
娘には責任を持って必ず吹くように教えた。
楽器を肩からつり下げる器具も作った。
こうして娘は無事に自分の役割を果たした。
娘は自分の実力に合った権利を行使できたと思っている。
権利を行使できると娘は自信が持てた。
そして、権利を行使するためには少しの努力も必要なのだと分かった。
いかがでしたか。
作者は最後に、Aくんへの思いをこう綴(つづ)っています。
「Aくん、あのときは何もできずにごめんね。大切なことを教えてくれてありがとう。」
それでは、また。
今日は、北九州市が平成24年度に募集した
人権作文の入選作品の中にあったお話を紹介します。
三十年ほど前、教員として勤務していた幼稚園に、
知的障害のあるAくんが在籍していた。
Aくんは、自力歩行はできるが、言葉はなく、
口を開けていつもニコニコしていた。
子どもたちは、Aくんが何かできれば手をたたいて喜び、
できないことはこぞって手伝い、
彼と共に過ごす中で心も大きく育っていった。
ある日、Aくんの担任からこんな話を聞かされた。
生活発表会でAくんの鍵盤(けんばん)ハーモニカに細工をして、
音が出ないようにするのだという。
間違った音を鳴らされると曲が台無しだから、と。
生活発表会は園の一大イベントで、保護者の期待も高い。
合同演奏を成功させたい気持ちは分かるが、あんまりだ。
でも、私はどうすればよいか分からず、意見する勇気もなかった。
合同演奏は無事に披露され、大きな拍手を浴びた。
もしかしたらAくんは事実を知っていて、
私たちの心の未熟さを黙って受け入れてくれたのではないか…。
そう思ったのは、その後、私自身が知的障害のある娘の母となったからだ。
娘を育てた時代は、社会も教育現場も、
少しずつ障害者の人権が重視されるようになっていた。
娘が小学六年生のとき、運動会で鼓笛(こてき)パレードがあった。
娘は、みんなと同じように歩きながら鍵盤ハーモニカを吹くのは難しい。
だからといって、障害を理由に娘がみんなの鼓笛パレードを
台無しにするようなことがあってはならない。
そこで私は先生に相談し、娘にも吹けるようにオリジナルの譜面を作り直し、
娘には責任を持って必ず吹くように教えた。
楽器を肩からつり下げる器具も作った。
こうして娘は無事に自分の役割を果たした。
娘は自分の実力に合った権利を行使できたと思っている。
権利を行使できると娘は自信が持てた。
そして、権利を行使するためには少しの努力も必要なのだと分かった。
いかがでしたか。
作者は最後に、Aくんへの思いをこう綴(つづ)っています。
「Aくん、あのときは何もできずにごめんね。大切なことを教えてくれてありがとう。」
それでは、また。


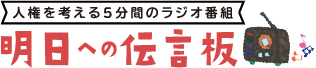


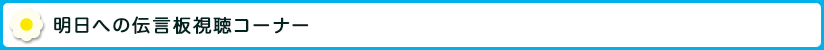
 2013年11月19日(火)放送
2013年11月19日(火)放送