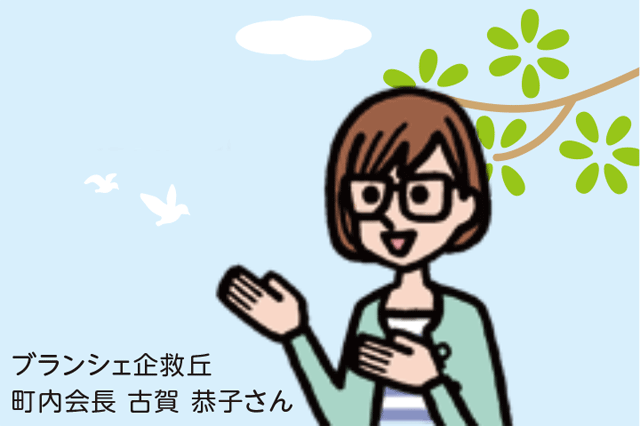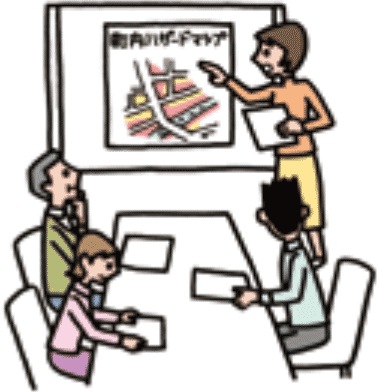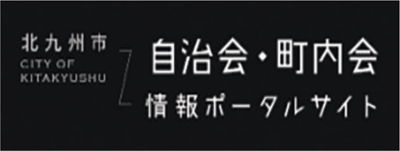「活動内容がわからない」「活動が大変そう」…。自治会・町内会について聞かれる声です。しかし、その一方で災害のときなどは自治会・町内会が持つ地域のつながりが大事といった声も聞かれます。
市内には約2800の自治会・町内会があり、日々、自分たちの手で安全・安心な住みよいまちをつくり、維持する、地道ではあるけれども大切な活動を行っています。今号では、新たなカタチ「マンション町内会」の地域活動などをご紹介します。
私たち、町内会をつくりました
「お互いさま」の関係づくりから、日々の安心と暮らしやすさが広がります。
~マンションにおける町内会活動~
町内会に参加するには、住んでいる地域の町内会に入ることが一般的ですが、戸数が多い分譲マンションなどでは、集合住宅の建物単位で町内会を立ち上げるケースもあります。小倉南区の「ブランシェ企救丘町内会」もその一つ。町内会発足の経緯や活動について、会長の古賀さんにお話を伺いました。
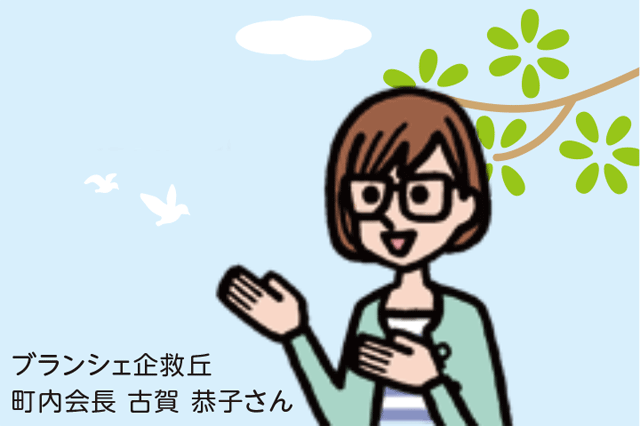
町内会発足のきっかけは?
分譲開始後に入居したマンションは、30~40代の子育て世帯が多いマンションでした。会合に参加したところ、200戸以上と戸数が多いこともあって、「マンションで新しく町内会を立ち上げてください」と言われ、その会合に出ていた数人が町内会準備委員会として活動を始めました。
具体的な活動内容は?
町内会を一からつくるのは初めての経験。校区自治会や市の担当者の方に教わりながら、1年をかけて準備しました。設立の目的は、まずは顔見知りを増やすこと。以前住んでいた地域でも、町内会活動を通じて知人の輪が広がり、ご近所さんが子どもたちを知っている安心感がありました。そこで、マンションの住民が参加しやすい親睦行事やごみ拾いイベントなどを実施。活動報告などを知らせる広報紙「ブランシェだより」も年に数回発行しています。
町内会を立ち上げて「よかった!」と思えることは?
住民どうしのつながりが深まったことです。校区の球技大会参加をきっかけにつくったソフトボールチームや、デイキャンプ、年末のもちつき大会(近年はコロナ禍で自粛)は好評です。子どもたちの歓声や「知り合いが増えました」といった話を聞くと、マンション町内会をつくってよかったなと思いますね。
また、マンション町内会として参加する校区自治会の会合や行事を通じて地域の人脈が広がりました。おかげで今では、困ったときに相談に乗ってもらえる知り合いが地域に何人もできました。マンション内だけでなく地域にも、会えば挨拶を交わせる「お互いさま」の関係が広がり、日々生活していく上での安心感が高まりました。
一方、組分けをしておらず組長という役職もなかったので、役員や一部の会員に負担が集中していることが課題になりました。そこで2年前に、輪番制の実行委員制度を導入。気軽に参加できるような改革にも取り組みました。今後、役を引き受けてくれる人が増えてスムーズな運営につながればと考えています。

今後、力を入れたいことは?
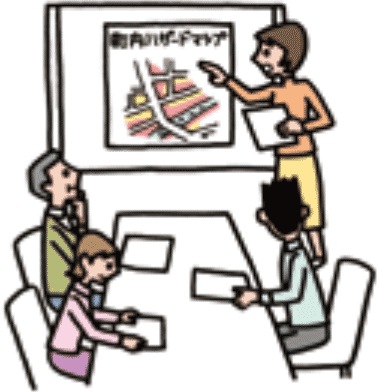
熊本地震では、自治会・町内会の防災活動が盛んな地域ほど、避難所でのトラブルが少なかったそうです。親睦も大切ですが、いざという時に助け合える信頼関係を育てることも、自治会・町内会活動の大きな役割です。今後は今まで以上に、防災・防犯関連の取り組みに力を入れていきたいと考えています。
市はマンションの町内会づくりを支援しています。
「分譲マンションで町内会を立ち上げるためにはどうしたらいいの?」といったお悩みを解消するため、市では、専門家を派遣しています。詳しくは、お住まいの区のコミュニティ支援課へ。
大学生が考える自治会ってなに?
地域の一員である若者たちも「地域のつながりの大切さ」を感じています。自治会・町内会のことを考える活動を行っている市内の大学生 西岡さんと柴野さんに、自治会について聞いてみました。

▲大学生の皆さんたち(後列 左から2人目 西岡蘭さん、同3人目 柴野雅人さん)
自治会に関心をもったきっかけは?

大学入学と同時にコロナ禍となり、授業はすべてオンラインに。登校も遠出もままならない中、あらためて自分が住むまちについて考えたのが始まりです。地域の現状、たとえば独り暮らしのお年寄りが集まる機会や気軽に訪れる場所がなくて寂しい思いをしていることなどを知って、“ご近所さんの交流の場”の必要性を強く感じました。若い世代の一人として、そうした活動を行う自治会活動を盛り上げるために何かできないかと考えました。(柴野さん)
自治会についてどう思っていたか?
正直、以前はまったく関心がありませんでした。ただ、僕は市内で生まれ育ったのですが、小学生の頃、楽しかった子ども会の行事など地域の大人たち(自治会)ががんばってしてくれていた活動が今は少なくなったと聞いて、ショックを受けました。隣近所、顔も知らない、挨拶もしないような間柄では寂しすぎます。(柴野さん)
自治会の加入率を上げたい!と思って始めた取り組みは?
自治会を知るには、まず興味をもつことが先決。そこで、楽しく遊びながら自治会活動について学べる、すごろくスタイルのボードゲーム「ナンジチ?!」を制作しています。「なんする?!自治会長人生ゲーム」、略して「ナンジチ?!」です。
「防犯灯がほしい!」「ごみステーションが汚い!」「台風が直撃しそうだ!」など、すごろくのマスごとに発生する地域のお困りごとに対処する自治会長(参加者)の奮闘を通して、自治会の活動内容が自然と理解できる仕組みです。制作にあたって、市内の自治会長に何度も話を伺いました。
「ナンジチ?!」は、3月に小倉南区の市民センターで試作品のお披露目をしました。今後は親子で楽しむゲーム体験や小中学生にも遊びながら学んでもらうイベントを考えています。(西岡さん、柴野さん)

▲「ナンジチ?!」お披露目会
取り組みを通じての感想、将来への思い
子どもの頃のように、活気に満ちた自治会がまた増えたらいいと思うようになりました。自治会活動を通じて地域のつながりが深まれば、誰もが自分のまちをもっと好きになれると思います。そのためにも、今後はもっと加入者が増えてほしいという思いはあります。大学卒業後も何らかの形で地域活動に関わっていきたいと考えています。(西岡さん、柴野さん)
自治会・町内会の活動をもっと詳しく知りたい
住みよいまちにするためにどのようなことに取り組んでいるか自治会や町内会の活動事例を知ることができます。
北九州市自治会・町内会情報ポータルサイト
自治会・町内会の活動紹介からお知らせまで、自治会・町内会に関することが分かるウェブサイトです。
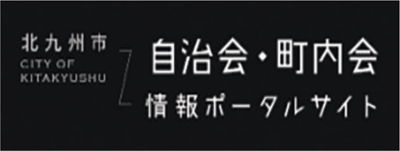
掲載記事の一例
災害時に頼りになる自治会~牧山地区自治会の取り組み
居住区域の多くを傾斜地が占める牧山地区自治会(戸畑区)では、「みんなで防災」を合言葉に「自然災害犠牲者を出さない」取り組みを進めています。市から派遣された専門家と協同で危険箇所の情報収集と分析を行い、毎年、地域に情報提供しています。また、避難所が開設されると、不自由がないか、避難方法はどうだったかなどを尋ね、安心できる避難所運営を行っています。この取り組みが地域のつながりを再び深めているそうです。

キタキュウ地域・人づくりチャンネル(YouTube)
地域の取り組みを発信し、魅力を伝える動画サイトです。
自治会・町内会や地域活動に関心を持っていただけるよう情報を発信しています。