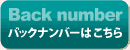【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】
北九州技の達人を認定(敬称略)
本市では暮らしに身近な分野を含む全ての産業分野を対象に、産業振興や市民生活の向上に貢献している優れた人を認定・表彰しています。
- ●小長光証=バーテンダー
- ●島田暄子=婦人服仕立職
- ●平成孝=調理師(西洋料理、氷彫刻)
- ●久恒揚吉=畳工
- ●三重野直=調理師(西洋料理)
- ●村山幸穂=ピアノ調律師
- ●幸縁=和服仕立職
問い合わせは産業経済局雇用政策課 TEL093・582・2419へ。

▲小長光証さん

▲島田暄子さん

▲平成孝さん

▲久恒揚吉さん

▲三重野直さん

▲村山幸穂さん

▲幸縁さん
市立霊園の使用者を募集
市立霊園は1家族につき1区画だけ利用できる、市が管理する霊園です。同一区画に複数の応募があった場合は抽選を行います。
なお、市立霊園では永代供養は行っていません。
対象者
祭祀(さいし)の主宰者で市内に住所か本籍があり、2親等以内の焼骨を持つ人など。同一世帯などでの重複申し込みは不可。平成5年以降に3回以上落選した人には、当選確率の優遇措置があります。
募集要項の配布
各区役所まちづくり整備課で配布中。市のホームページからもダウンロードできます。郵送を希望する人は住所・氏名を書いて〒803―8501建設局公園管理課へ140円切手を送付してください
申込期間
1月16~27日
申込方法
郵送(建設局公園管理課で受け付け)かネット窓口(電子申請)で。一般墓所は、希望する区画(使用場所)が選べますので事前に現地を確認してください。納骨堂と共同墓碑の区画は選べません。申し込みが無い区画は、3月2日から随時募集(先着順)を行います。詳細は問い合わせを。
申込状況の公表
1月23日に申し込み状況を市の市のホームページで公開します。
問い合わせは建設局公園管理課 TEL093・582・2464へ。
平成28年度 市立霊園の募集区画
| 区 | 霊園名 | 募集 予定数 |
施設名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 墓所 | 納骨堂 | 共同墓碑 | |||
| 門司 | 城山 | 24 | 19 | 5 | - |
| 小倉北 | 足立 | 18 | 14 | 4 | - |
| 若松 | 小田山 | 11 | 6 | - | 5 |
| 小石 | 4 | 4 | - | - | |
| 藤ノ木 | 14 | 3 | - | 11 | |
| 八幡東 | 谷口 | 30 | 26 | 4 | - |
| 八幡西 | 十三塚 | 23 | 23 | - | - |
| 戸畑 | 高峰 | 35 | 26 | 3 | 6 |
| 中原 | 16 | 12 | 4 | - | |
問い合わせは産業経済局食の魅力創造・発信室 TEL093・582・2080
旬を食べよう! 地元いちばん

井上泰三さん
北九州の郷土料理「ぬか炊き」を地域の食文化として市内外に発信していこうと、昨年北九州ぬか炊き文化振興協会が発足しました。同協会会長の井上泰三さん(山一物産)にぬか炊きについて話を聞きました。
■全国でも珍しい、ぬかみそを加えて青魚を炊き込む「ぬか炊き」
ぬか炊きは、江戸時代から豊前国に伝わる伝統料理です。全国的にぬかみそを調味料として炊き込む料理は珍しく、小倉城下に伝わる独自の食文化と言えます。
■ぬか床のルーツは江戸時代

サバのぬか炊き
ぬか床の初見資料は江戸時代初期で、小倉城を築城した細川忠興とその息子・忠利との間の書状に「ぬかみその味がよく、満足した」旨の記述が残っています。その後、小笠原氏の初代藩主・忠真もぬか漬けを好み、この頃にぬか漬けが城下へ広まったと言われています。
ぬか炊きのルーツは定かではありませんが、豊前地方には生のイワシを塩とぬかで漬け込む「へしこ」に近い食文化があり、ぬか炊きへと調理法が変化したとも考えられます。
■ぬか炊きは健康を保つ栄養素がたっぷり
ぬか炊きは、ぬかみそと青魚の栄養を丸ごと取ることができます。整腸作用やカルシウム吸収促進などの効果が見込まれ、青魚から溶け出した必須脂肪酸が含まれる煮汁と一緒に食べるとさらに栄養価がアップします。
■北九州ぬか炊き文化振興協会の活動

▲「福岡のおいしい幸せ」大晩餐会にてぬか小町が小川福岡県知事(写真中央)と一緒にぬか炊きをPR
家庭で作られてきたぬか炊きは、ぬか床の保有率の減少とともに家庭料理として登場する機会が減ってきました。一方、ぬか炊きを作る事業者や飲食店は徐々に増えてきており、これらの事業者が協会を結成し、ぬか炊きを地域の名産品としてPRしていこうと活動を開始しています。
問い合わせは同協会 TEL093・372・7939(山一物産)へ。
|1ページ|2ページ|