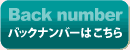![]() 懐かしくて新しい おめでたい遊び
懐かしくて新しい おめでたい遊び

本市が誕生して55周年となる平成30年がやってきました。この節目のお正月を、皆さんはどのように過ごしていますか。家族や友人が集まることの多いお正月に、みんなで昔から伝わる遊びを学び、楽しんでみませんか。大人には懐かしく、子どもには新しい、お正月の遊びの一部を紹介します。
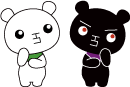
ていたん&ブラックていたん
お正月の遊びには由来があるんだね
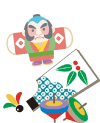

たこ揚げ
紀元前2世紀頃の中国で、大きな「たこ」を敵陣まで飛ばしたのが始まりといわれ、日本へは平安時代に伝わりました。地域によって「いか」や「たつ」、「はた」などの名で呼ばれたそうです。江戸時代に大流行し、絹張りをしたものや、金銀をちりばめたものなどさまざまなたこが登場しました。子どもの成長を祝い、幸せな将来を祈って誕生祝いに揚げたともいわれています。

こま
こまの由来には諸説がありますが、一説には唐の時代の中国から朝鮮半島の高麗を経て日本に伝わり、当時の高麗の呼び名「こま」が、語源となったといわれています。遊びだけでなく、吉凶を占う道具として使われることもありました。伝わった当時は宮廷での貴族の遊びでしたが、江戸時代には庶民の間に広がったようです。

羽根つき
昔は蚊などが病気を運ぶと信じられていたため、「ムクロジ」の木の種に羽を付けて蚊を食べるトンボに似せ、これを打ち合って、厄病除けのまじないとしたのが始まりといわれています。江戸時代になると、歌舞伎の人気役者などの絵が押し絵された飾り羽子板が人気を博しました。ムクロジは無患子(子が患わない)と書くことから子どもを病気から守る意味があったと考えられます。
◆たこを作ってみよう


官兵衛タン
左右のバランスが大事だよ

用意するもの
- ●和紙(破れにくければ可)たこの本体50cm×30cm1枚 たこの足70cm×5cm2枚
- ●竹ひご(細い棒なら可)50cm3本、30cm1本
- ●セロハンテープ、たこ糸

(1)50cmの竹ひごを、たこの本体の左右にセロハンテープで貼り付けます。

(2)たこの本体の中心に50cmの竹ひごを縦に置き、30cmの竹ひごを横にして、上から3分の1の所に置きます。竹ひごの上下左右をセロハンテープで貼り付けます。

(3)たこの足をたこの本体の左右両端に1枚ずつ貼り付けます。

(4)たこ糸を写真(4)のように竹ひごに結び付けます。裏返して上下左右の長さがそれぞれバランス良くなるようにたこ糸を1本にまとめます。
◆市内でたこ揚げができる場所の一例

- ●勝山公園大芝生広場(市役所南側)
- ●大橋公園(戸畑区川代2丁目)
※車や電線など、周囲の安全を必ず確認しましょう。

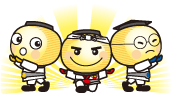
とばた宣隊 ちょうちんジャー
遊びの中に伝わる工芸品
●孫次凧(まごじだこ)
竹内義博さん(北九州技の達人)
「孫次」は、私の祖父の名前です。北九州は冬の季節風が強くて、昔からたこ揚げが盛んだったんですよ。たこ職人は大勢いましたが、祖父のたこは、よく揚がることに加えて大きく可愛い目のセミやフグなど、他にはない形と独特な色彩が評判でした。
今でも当時と同じように一つ一つ全て手作業で、地元の真竹や女竹と八女などの手すき和紙を使い、自然素材の食紅で彩色して作り上げています。
伝統の技を守ることは大変ですが、たこ揚げをしている子どもたちの笑顔を見るのがうれしくて作り続けています。このお正月もぜひたこ揚げを楽しんでもらいたいですね。
今年の干支「戌」(いぬ)のミニ孫次凧を3人に進呈します。
協力:カイトハウスまごじ(戸畑区新池1丁目)

【応募方法】
はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、「孫次凧希望」と書いて1月5日(金)までに〒803―8501広報室広報課へ。

モモマルくん
遊びにはいろいろな願いが込められているよ


お手玉
お手玉の歴史は古く、紀元前5世紀には遊ばれていたという説があります。その当時は「羊の足の骨」を使って遊んでいました。日本には奈良時代に伝わり、身近にあった「石」が使われるようになりました。今のような布のお手玉が登場するのは江戸時代後半からで、大豆やじゅず玉などを入れていました。主食のコメを入れる俵をかたどった俵型のお手玉は、豊作を願って作られたのかもしれません。

福笑い
明治時代にはお正月の遊びとして盛んに行なわれたそうです。伝統的な「おかめ」「おたふく」といわれるお福面の顔だけでなく、アニメの主人公や家族の顔などを使って自由に作ることができる遊びです。「笑う門には福来る」ということわざにあるように、正月に笑うことで、この1年を笑顔で過ごせる福を呼び込みたいという願いが込められています。

かるた
お正月のかるたと聞くと、小倉百人一首の歌がるたを思い出す人が多いかも知れません。平安時代に行われた貝合(かいあわせ)が起源といわれ、江戸時代初期に一般に広まりました。
「犬も歩けば棒に当たる」の犬棒カルタが有名な「いろはかるた」は江戸時代後期に始まったといわれています。子どもが楽しく文字やことわざを覚えられるように考えられたのではないでしょうか。
◆お手玉を作ってみよう


じーも
ここでは俵型のお手玉を紹介するよ

用意するもの(1個分)
- ●長方形の布 (10cm×16cm程度)
- ●針、糸
- ●アズキ40g

(1)内側が表地になるように布を縦長に半分に折り、長辺の端を縫います。

(2)短辺の端を縫った後、糸を締めて布をきゅっと縫い縮めます。

(3)縫い目に注意しながら内と外を裏返し、アズキをその中に(8分目くらい)入れます。

(4)最後に反対側の端を縫った後、糸を締めて布を縮めます。
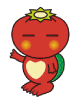
わかっぱ
「北九州市ふるさとかるた」を知っていますか
「北九州市ふるさとかるた」には、北九州自慢がいっぱいです。市内の名所・旧跡や食をテーマとした絵札と市民公募による読み句で、子どもから年長者までが、遊び楽しみながら、本市の魅力や歴史、文化を再発見できます。未来を担う子どもたちに、故郷に対する愛着や誇りを持ってもらおうと、この「北九州市ふるさとかるた」を使った小学生かるた大会(主催:北九州市にぎわいづくり懇話会)が毎年開催されています。
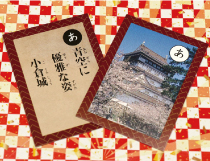
●読み句例
![]() 提灯で 五色に焦がす 戸畑の夜
提灯で 五色に焦がす 戸畑の夜
![]() 古き佳き 時代とどめて 門司港駅
古き佳き 時代とどめて 門司港駅
![]() 凛とたつ 東田高炉 技の街
凛とたつ 東田高炉 技の街
![]() 若戸大橋 洞海湾を ひとまたぎ
若戸大橋 洞海湾を ひとまたぎ
「北九州市ふるさとかるた」とノートを3人に進呈します。
提供:北九州市にぎわいづくり懇話会
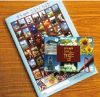
【応募方法】
はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、「ふるさとかるた希望」と書いて1月5日(金)までに〒803―8501広報室広報課へ。
※遊びの由来には諸説があります。
【参考文献】
- ・藍尚禮 他(1984)『日本大百科全書』小学館
- ・相賀徹夫編(1978)『大日本百科事典』小学館
- ・大西伝一郎(1997)『お手玉』日本お手玉の会監修、文溪堂
- ・下中邦彦編(1977)『国民百科事典』平凡社
- ・多田敏捷編(1992)『おもちゃ博物館』京都書院