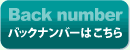【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】
ゴールデンウイーク期間中の救急医療体制
問い合わせはテレフォンセンター 電話093・522・9999
各診療科目の受け付けは、診療終了時間の30分前まで(24時間診療の医療機関は除く)です。受診する科や症状(緊急度)によっては待ち時間が長くなることがあります。
下記以外の医療機関でも内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科などの診療を行っている場合があります。詳細は、テレフォンセンターへ問い合わせを。
| 救急医療機関 | 診療科目 | 4月27日(土) | 4月28日(日) | 4月29日(祝) | 4月30日(休) | 5月1日(祝) | 5月2日(休) | 5月3日(祝) | 5月4日(祝) | 5月5日(祝) | 5月6日(休) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
夜間・休日急患センター 小倉北区馬借1丁目7―1 【総合保健福祉センター1階】 電話093・522・9999 ※眼科は他の医療機関を紹介する場合が あります。事前に問い合わせを |
内科、小児科、 外科・整形外科 |
19時30分~ 23時30分 |
9~23時30分 | |||||||||
| 眼科※ | ||||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||
| 歯科 | - | 9~17時 | ||||||||||
|
第2夜間・休日急患センター 八幡西区黒崎3丁目15―3 【コムシティ地下1階】 電話093・641・3119 |
内科、外科、 整形外科 |
19時30分~ 23時30分 |
9~23時30分 | |||||||||
| 休日 急患 診療所 |
【門司】門司区羽山1丁目1―24 電話093・381・9699 |
内科、小児科 | - | 9~17時 | ||||||||
| 【若松】若松区藤ノ木2丁目1―29 電話093・771・9989 |
||||||||||||
|
小児救急・小児総合医療センター 八幡東区尾倉2丁目6―2 【市立八幡病院内】 電話093・662・1759 |
小児科 | 24時間対応 | ||||||||||
| 北九州総合病院 小倉北区東城野町1―1 電話093・921・0560 |
9時~翌日7時 | 開院日 救急:17時~翌日7時 |
9時~翌日7時 | 開院日 救急:17時~翌日7時 |
9時~翌日7時 | |||||||
| 重症の場合は24時間対応 | ||||||||||||
|
国立病院機構小倉医療センター 小倉南区春ケ丘10―1 電話093・921・8881 |
24時間対応(受診前に問い合わせを) | |||||||||||
|
地域医療機能推進機構 九州病院 八幡西区岸の浦1丁目8―1 電話093・641・5111 |
9~24時(0~9時は事前に問い合わせを) | |||||||||||
●ゴールデンウイーク中に通常の診療を行っている医療機関がありますので、かかりつけ医の診療日時などを事前に確認しておきましょう。
●市は、医師会等の団体や産業医科大学病院、その他救急医療機関などの協力を得て、救急医療体制を運営しています。不要不急の受診を避けるなどご協力をお願いします。
●子どもの急なけが・病気については、福岡県小児救急医療電話相談(電話#8000)にご相談ください。受付時間は、19時(土曜日は12時、日曜日と祝・休日は7時)~翌日7時。19~23時は 電話093・662・6700も可。
●救急車を呼ぶべきか、病院を受診すべきか迷った場合は、福岡県救急電話相談・医療機関案内(電話#7119か 電話092・471・0099)をご利用ください(24時間対応)。
●ゴールデンウイーク期間中の市立病院の診療
医療センター(小倉北区馬借2丁目、電話093・541・1831)、八幡病院(八幡東区尾倉2丁目、電話093・662・6565)、門司病院(門司区南本町、電話093・381・3581)は4月27日(土)~29日(祝)、5月1日(祝)、5月3日(祝)~6日(休)は休院します。4月30日(休)、5月2日(休)は通常どおり開院し、診療します。問い合わせは病院機構 電話093・582・3051へ。
麻しん(はしか)を予防しましょう
全国的に、麻しん(はしか)の患者が増えており、特に東南アジアなどの麻しん流行地域から、日本国内に持ち込まれることによる感染(輸入感染)が広がっています。平成30年の麻しん患者は、市内では0人でしたが、福岡県内では20人の患者が報告されました。
麻しんってどんな病気?

- 麻しんは、感染力が非常に強く、空気、飛沫(ひまつ)(くしゃみなどのしぶき)、接触によって感染します。
- 免疫の不十分な人が感染すると、ほぼ100%発症します。
- 症状は、高熱や全身の発疹、せき、鼻水、目の充血などです。
- 肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症を伴う場合があり、死亡例もあります。
- 効果的な治療薬はないため、症状を抑える対症療法での治療が中心です。
医療機関で受診を
東南アジア等、麻しん流行地域に行ったことがある人で、発熱、風邪症状、目の充血、発疹などの麻しんを疑う症状がある場合は、医療機関へ連絡の上、受診してください。また、受診の際は、自家用車などを使用し、できるだけ公共交通機関の利用を避けましょう。
医療機関へは、(1)流行地域での滞在歴、(2)麻しん含有ワクチンの接種歴〈麻しん単独ワクチン、MR(麻しん風しん混合)ワクチン等〉、(3)麻しん罹患(りかん)歴(過去にかかったことがあるかどうか)などを伝えましょう。
麻しんを予防するためには?

手洗い、マスクだけでは予防できません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。
- 今まで麻しんにかかったことがない
- 麻しんの予防接種歴が不明
- 麻しんの予防接種を1回しか受けていない
※これらに該当する人は麻しんの予防接種を検討してください。
定期予防接種の対象者は無料で受けることができます
【対象者】1歳児と小学校就学前の1年間(年長児)。
※対象者以外は、自費負担での接種となります。
問い合わせは保健福祉局保健衛生課 電話093・582・2430へ。
|1ページ|2ページ|