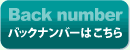【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】
国民健康保険料のお知らせ
平成31年度の国民健康保険料(均等割額、平等割額)を下表のとおり決定しました。
所得割額を含めた平成31年度の国民健康保険料は、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。
介護分の対象は、国民健康保険に加入している40~64歳の被保険者です。
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
|---|---|---|---|
| 均等割額(被保険者1人の額) | 2万270円 | 7180円 | 7730円 |
| 平等割額(1世帯の額) | 2万3790円 | 8550円 | 6930円 |
| 所得割額 | 世帯の被保険者全員の平成30年分の所得に応じて算出。料率は5月末に決定。 | ||
| 賦課限度額 | 61万円 | 19万円 | 16万円 |
※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。
※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため国民健康保険に単身加入となる世帯について、平等割額を軽減します。
平成31年度の主な改正点
医療分の賦課限度額が3万円引き上がり61万円になります(後期高齢者支援金分と介護分の賦課限度額の19万円と16万円は変わりません)。
低所得者に対する国民健康保険料の軽減について
国の定める所得基準を下回る世帯は保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯かどうかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。
| 軽減割合 | 軽減の基準(前年中の所得)(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の前年中の合計所得) |
|---|---|
| 7割 | 合計所得が、33万円以下の場合 |
| 5割 | 合計所得が、33万円+(28万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合 |
| 2割 | 合計所得が、33万円+(51万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合 |
※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。
※擬制世帯主とは、国保被保険者の属する世帯で、世帯主が国保の被保険者でない場合の世帯主のことです。
平成31年度の改正点
5割軽減と2割軽減の軽減対象の範囲が変わります。加入者1人当たりの基準額が、5割軽減については27万5000円から28万円に、2割軽減については50万円から51万円になります。
問い合わせは各区役所国保年金課へ。
後期高齢者医療保険料のお知らせ
平成31年度保険料の料率と軽減
●保険料率
保険料(年額)の計算式=均等割額(5万6085円)+所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)-33万円】×10.83%)。賦課限度額は62万円。
(※1)前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額。
●均等割額の軽減
世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。
本則7割軽減の対象の人は、軽減割合を上乗せして8.5割軽減、9割軽減とされてきましたが、年金生活者支援給付金の支給が開始されることなどにより、軽減割合が見直されます。
| 軽減割合(均等割額の年額) | 対象者の所得要件[同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額] | ||
|---|---|---|---|
| 本則 | 平成31年度 | ||
| 7割(16,825円) | 8.5割(8,412円) | 【平成30年度における8.5割軽減区分(※3)】33万円以下 | |
| 8割(11,217円) | 【平成30年度における9割軽減区分】 うち、世帯の被保険者全員の年金収入が80万円以下で、その他各種所得なし |
||
| 5割(28,042円) | 5割(28,042円) | [33万円(基礎控除額)+28万円×被保険者数]以下 | |
| 2割(44,868円) | 2割(44,868円) | [33万円(基礎控除額)+51万円×被保険者数]以下 | |
(※2)基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。
(※3)年金生活者支援給付金の支給の対象とならないなどを踏まえ、激変緩和の観点から、1年間に限り実質上8.5割軽減は据え置かれることとなりました。
●後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険(※4)の被扶養者であった人の軽減
制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され(※5)、所得割額はかかりません。
(※4)国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
(※5)均等割額の軽減が所得により8.5割軽減、8割軽減に該当する人は、それぞれ8.5割軽減、8割軽減が優先されます。
平成31年度保険料の納付
- 2月に年金天引きだった人 原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、平成30年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、平成30年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
- 2月に年金天引きでなかった人 原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。
なお、4月上旬に「平成31年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。
問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 電話092651・3111か各区役所国保年金課へ。
固定資産税ゼロ特例事業の相談・受け付け
中小企業などの新規取得設備の固定資産税が、3年間ゼロになる制度の受け付けをしています。この特例を受けるためには先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。
(1)先端設備等導入計画の提出
計画期間内(3~5年)に労働生産性を年平均3%以上向上させるための先端設備など(生産、販売活動などの用に直接供される新規の減価償却資産。一定の要件あり)を導入する計画を策定し、それを本市が認定します。
(2)計画の認定を受けられる事業者
対象 中小企業等経営強化法上の中小企業など。ただし、固定資産税のゼロ特例を利用できるのは資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主など(大企業の子会社を除く)。
(3)計画の認定を受けた場合の効果

- 認定を受けた先端設備などの固定資産税が3年間ゼロになります。
- 国の補助金(ものづくり補助金)の補助率が2分の1から3分の2になります。
- 国の補助金(ものづくり補助金)の優先採択があります。
申し込みは随時(祝・休日を除く月~金曜日の8時30分~17時15分)。詳細は産業経済局中小企業振興課 電話093・873・1433へ。※申請方法・申請様式などは市のホームページをご覧ください。
|1ページ|2ページ|