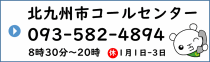令和7年3月28日(金曜日)14時00分から15時30分まで
第59回北九州市環境影響評価審査会議事要旨(令和7年3月28日)
1 日時
2 開催方式
ウェブ会議
3 出席者
委員
藍川委員、伊藤委員、岩松委員、岡本委員、川﨑委員、北沢委員、楠田会長、柴田委員、副島委員、田中委員、豊貞委員、内藤委員、三笠委員、蓑島委員、村瀬委員
事業者
株式会社グローカル、海洋エンジニアリング株式会社
事務局
環境局環境監視部環境監視課(環境監視部長ほか4名)
4 議題
「(仮称)北九州市白島沖浮体式洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」の審査
5 議事要旨
(楠田会長)
それでは、ただいまから審議に入らせていただきます。
まず初めに、事前に頂戴いたしましたご意見がございますので、意見を出してくださった委員の方からご発言を頂戴したいと思います。
それでは、まずは岩松委員お願いします。
(岩松委員)
よろしくお願いします。
1つ目は水産資源への影響評価ということで、生態系への影響についてお尋ねしたいと思います。近年、気候変動などが言われまして、水温の変化などの海洋環境というのがますます変化している中で、北九州の海域でもこうした声が現在聞かれるところです。もちろん、今そういったすべての海洋資源の変化というのを今回のアセスで調べることは難しいのですが、その海洋資源を考える上で、水産資源のデータを綿密に分析されていくということが大事だと思います。過去からの変遷のデータ、そして新しい2023年漁業センサス等もそろそろ出てくるのではないかと思いますが、そうした結果、数値データを用いて、きめ細かく分析していく必要があるのではないかと思っています。そして、現地調査もできるだけ効率的な方法で行うことが可能であれば、そちらを実施していただければと思いますし、また関係者からの聞き取りが欠かせないと思っています。
これは2つ目の質問に繋がるのですが、まず1つ目の方からお願いできましたらと思います。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
では、事業者から回答を頂戴いたします。
(事業者)
承知いたしました。
ご指摘の通り、水産資源につきましては、近年、海洋環境の変化により影響を受けていることも考えられますので、漁獲量データを収集しまして、バックグラウンドの把握に努めて参りたいと思います。一方で、風車による魚類への予測評価についてですが、他の事業の事後調査結果等を引用する方法や風車が発生する水中音に対する魚類の聴覚特性等を基にする方法が提示されております。これは環境省や経産省が技術ガイドとして作成したものの中にありますので、そういったものを利用しながら、現地のデータを活用しながら予測評価を実施して参りたいと考えております。
以上でございます。
(岩松委員)
はい。ありがとうございます。
他の調査を参照されるということなのですが、やはり北九州の海域独自の情報というのがたくさんあると考えられますので、水産関係者及び広く関係者の方からの聞き取りを基に分析をしていただけたらと思っています。
そして、2つ目に繋がるのですが、事業実施想定区域が漁業法における共同漁業権内であることに対して、海域占用に対する関する調整協議が必要というふうに書かれていますが、予定されている調査項目、協議方法などについて教えていただけたらと思います。
(事業者)
ご質問ありがとうございます。
現在、任意の協議会という形にはなりますが、地域協調型の浮体式洋上風力導入推進協議会というものの開催を準備しております。正式には、令和7年度実施することとしておりまして、先般その準備会を開催したところでございます。協議会のメンバーといたしましては、関係機関として北九州市、福岡県、若松海上保安部、地元関係者、関係企業、住民代表として、北九州市漁協、地域新電力会社、用地関係者、白島国家石油備蓄基地、あとは大学研究機関といたしまして、東京大学、北九州市立大学、佐賀大学から関連する教授の方々にも、参加を要請しているところでございます。またオブザーバーとして、環境省にもご参加をいただき、協議内容の必要に応じて、経産省、国交省への参加をお願いすることを想定している状況でございます。
協議会を通じて、本事業に関して関係者の皆様のご理解を深めるとともに、本事業における技術的、経済的、社会的な課題を共有し、それらを解決し、再生可能エネルギーの地産地消の実現の手法やこの事業から発生する水産振興、地域振興のあり方等について協議を行い、持続可能な再生可能エネルギービジネスモデルの構築を念頭に事業の実現可能性を評価するような場として考えてございます。
共同漁業権内における事業実施の可否につきましては、協議会を通じて洋上風力発電事業と漁業との共存共栄の在り方、漁業者の発電事業への参画の可能性などについても議論し、ご意見やご提案をいただく中で着地点を見いだし、事業実施に向けたご同意をいただきたいと思います。
以上でございます。
(岩松委員)
どうもありがとうございます。協議会をつくられるということで、大変よい方法であると考えます。
1点、特にお伝えしておきたい点があります。今回の漁業というのは社会的な状況ということで項目が挙がっているのですが、やはり漁業というのは自然に依拠した産業でありまして、特に環境アセスの項目である景観及び人と自然との触れ合いの活動の場について、まさに漁業というのは自然と人が触れ合う場であり、その影響というのは自然または自然資源という面からの影響というものが関わっているということを、ぜひ考慮してくださればと思います。
そして北九州の漁業というのは大変長い歴史がある産業でございまして、かつ、今もなお、魚の食文化というのは市政においても重要であるという方向が打ち出されておりまして、ますます水産業の活性化が期待されている現状がある中で、今後どのように保護していくかというような岐路にあると理解しておりますので、そういった中での自然と社会そしてこの地元の歴史というところが、まさに人と自然の触れ合いの場ということの保全に繋がると思いますので、その点でのご配慮お願いしたいということ。また、今回協議会には様々な方々が参加のご予定ということで、大変それはありがたいのですが、今回のこの漁業権が設定されているところ以外の漁業権に関わる方々というのも、ぜひ何らかの意見を出しやすい場にしてくださるとありがたいと思っています。
といいますのは、この先、1基2基3基というふうに計画を立てられているのですが、この先もこの海域に様々な風車が立つということを想定しますと、今回のプロセスまたは漁業とのあり方というような方法が続いていく第一歩になり、前例になるという重要なポイントでありまして、ぜひ関係者を広く、多くの方の意見を出しやすい形での協議会にしてくださるとありがたいと思っています。
以上です。よろしくお願いいたします。
(楠田会長)
はい。岩松委員、どうもありがとうございました。
事業者から何かございますか。
(事業者)
はい、ご意見ありがとうございました。
いただいた意見をもとに協議会への参加者の範囲について、複数の漁業権に広げて漁業者の方々のご意見を伺えるような場を作っていきたいと思いましたので、今後の協議会を進めていく上での参考とさせていただきながら進めさせていただきたいというふうに思います。
(楠田会長)
はい。岩松委員、追加はございますか。よろしいでしょうか。
(岩松委員)
大丈夫です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございました。
それでは、次のご発言を頂戴いたします。ご意見は川﨑委員からいただいておりますので、川﨑委員お願いいたします。
(川﨑委員)
私のほうからは意見を3つほど出しております。
事業実施想定区域が、前回の着床式の計画の場所から少し沖合に伸びているが、ほとんど変わっていないということで、白島で繁殖するオオミズナギドリ、ミサゴ、冬場渡来するウ類へのバードストライクの危険性が全く低下してないのではないかということを心配しております。大体直径が最大290メートル、水面から25ないし40メートルの高さを毎分12.4回転するという回転翼において、羽根の先端の速度を計算しますと時速607キロから677キロということです。その速さが直感的にわかりにくいのですが、リニア新幹線の時速が500キロというスピードで、それよりも速いスピードで回転翼がおりてくる。鳥の中ではハヤブサが一番速いスピードだと言われておりますが、それでも時速390キロです。とてつもなく速いスピードで、一番回転の速い時がそういう形で回転するという状況です。
また、配慮書の5-8ページにある図5.1-4に、白島周辺のオオミズナギドリの飛翔経路が載せてあるのですが、この図には建設予定地の位置が設置されておりません。他の図はいろんな図面を引用して作って建設予定地をそこに図示しているのですが、これについてはNEDOの調査の図をそのまま掲載しておりまして、図を落とすと右上部分、図の3分の1が予定区域に入りますので、NEDOの調査ではオオミズナギドリがかなり飛び交うところに建設するような計画になるということで、そのあたりが心配なところでございます。
それから、建設予定地を白島周辺に固執する理由について、配慮書には共同漁業権が設定されているということで示されておりますが、バードストライクを避けるうえで、建設候補地をもっと白島から沖合あるいは西の方に離すことが、問題を少なくするという意味では非常に効果的だと思います。
2番目に、配慮書の5-2ページにおいて、実施想定区域でのオオミズナギドリの個体数を年間300個体との数字で出しております。この数字がどこから来たかというのは説明資料読んでも出てきませんので、なにを根拠に年間300個体という数字を出しているのかという点です。この数字は5-15ページにあります表5.1-9「バードストライクの計算に用いたパラメータ」にある高度M通過頻度(個体)に使われています。この根拠のない数字を用いてバードストライクの確率が年間1個体未満ということを出しているということで、それでいいのかという気がいたします。
意見票に書いていますように、日本野鳥の会北九州支部が1978年に県の委託を受けて、日本野鳥の会と北九州支部が一緒になって、個体数調査に取り組んだのですが、その調査と、最近では2021年に男島での個体数調査を実施しました。時間的に限られていたので非常に大まかな数字ですが、1978年は1,500巣、2021年は1,200巣、巣の数が推計されていて、1巣当たりペアで2個体が関わっているのであれば、それぞれ3,000羽あるいは2,400羽の個体が利用していると判断できます。この調査は簡易調査であるため正確な生息調査ということではないのですが、こういった数が白島を利用しているということが考えられるので、年間300個体という数がどこからきた数字なのかというのは確認したいなと思います。
それと、衝突確率についても、近くに特筆すべき環境のない洋上での衝突確率の考え方でありますので、例えばこの白島のような近くの繁殖地から飛び出すという、通常の洋上とは別の条件が大きく関わってくるところで洋上の予測衝突確率を使うことは適切ではないのではないかと考えられます。しかも、夜間に島に帰り、朝早く島を離れる鳥に対して、こういった衝突確率を使うことは適切ではないのではないかと思います。また、オオミズナギドリというのは巣に対する固着性が高いと言われておりまして、バードストライクで多くの個体が亡くなっても帰島行動を続ける可能性が高く、いわゆる風車に慣れて減少するということはなく、毎年それなりの数が減ってくのだと心配されます。
また、3番目になりますが、白島の男島の西側の岸壁は冬になりますと、ウミウやヒメウが多数越冬のために渡来するところです。これも先ほど言いました1978年に行った調査で26,100個体を推計して出しております。これは夜間調査に基づいて行っているので、ウ類の利用状況というのは把握しにくいですが、昔行った唯一の調査で26,100個体を推計しており、こういったウ類が今回の調査には全く入っておりませんので、どの程度の個体が現在も使っているのかというのもわかりません。このウ類が朝方飛び出すにあたって、通常はそんなに高い高度を飛ぶことはないのですが、気象条件次第では25メートル以上の飛行高度をとることは考えられますので、バードストライク防止のためには、夜間の生息状況を把握する必要があるのではないかと思いまして提案しております。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
では、事業者から回答を頂戴いたします。
(事業者)
まず1つ目のご意見ですが、事業実施想定区域の考え方につきましては、配慮書にも記載させていただいております。2-5ページから2-6ページに示しておりますが、この地域は北九州市における洋上風力発電に対する行政の積極的な取り組みがありますし、風況のよさ、事業性、環境の配慮等踏まえて、今の事業実施想定区域となる事業実施可能な範囲として設定させていただいております。一方でご指摘の通り、この白島は鳥獣保護区として指定されておりますので、白島周辺のオオミズナギドリ等の貴重な鳥類の繁殖地として重要な区域であることは認識しております。今後の環境アセスの手続きにおいては、適切な予測評価を行いまして、風車の配置等を検討した上で、事業計画を策定する所存でございます。
続きまして2つ目のご意見で、この300個体という根拠ですが、これにつきましては、配慮書の5-7ページに示させていただいております。これは既存資料でありますが、NEDOが実証事業で風車を建てるところで実施した調査結果でございまして、このときの年間のオオミズナギドリの分布図が、今回の事業区域に相当する場所には約300個体見られておりましたので、その数字を根拠として使わせていただきました。既存資料ではありますが、根拠の方はお示しできているかと思います。今後におきましては、さらに、現地の調査結果を踏まえた予測を行っていく所存でございます。
そして3つ目のウ類のお話ですが、いただいたご意見を参考にさせていただきまして、さらに情報の収集に努めて参りまして、ミサゴ、オオミズナギドリ以外の鳥類についても、リスクの高い鳥が確認された場合は、評価の対象として参りたいと考えております。
以上でございます。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
川﨑委員、何か追加のご発言ございますでしょうか。
(川﨑委員)
はい、先ほどの年間300個体という数字について、配慮書の5-7ページの資料で0から1キロメートル当たりで観察された数字、Cの側線というところとなっていますが、年間300個体というこの数字は、あくまでもトランセクト調査でカウントされた数字ということなのですよね。だから、昼間洋上に飛び立った後、餌場として、オオミズナギドリが洋上で生息する数を言っているわけです。私が言っているのは、今回、白島のすぐ近くで建設するわけですから、白島が一番近い距離にあるところで、どれだけのオオミズナギドリが生息しているか、その数を根拠にしない限り、洋上での年間300個体という数は、いわゆるバードストライクの確率を推定するには少しおかしいのではないかという気はするのです。白島のすぐ脇で建てるということであれば、繁殖時期に白島に集まっている個体の最大数、それがどう動くかというのが一番気になるところなので、そこをはっきりしない限り、この年間の衝突確率の出し方というのは少し納得いかないかなと思います。実際、NEDOの調査では白島周辺には相当な数のオオミズナギドリの移動軌跡が出ていますので、あれが年間300個体の軌跡なのか、という思いです。実際に調査した中ではあれだけの移動個体が見られているわけですから、もっと数字は多くなるのではないかと思います。そのあたりを今後もしっかり見ていただければと思います。
(楠田会長)
はい。ありがとうございました。
事業者側からのコメントはございますでしょうか。
(事業者)
今ご意見いただいた内容を参考にさせていただきまして、今後現地に近い白島周辺に注目した調査データもありますので、そういったものを活用しながら、実態を把握していければと思っております。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
川﨑委員それでよろしいでしょうか。
(川﨑委員)
皆さんの意見が出た後でまた何かありましたら、手を上げますのでよろしくお願いします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それでは続きまして、北沢委員のご発言を頂戴いたします。
(北沢委員)
大きく2点ございます。
まず事業目的なのですが、北九州市の重点施策として脱炭素電力の安定供給を目指されるということは非常に理解できるのですが、旧事業と本事業の違いがあまり明確ではないように感じています。本事業がどういうふうに必要性があるのか。あと、現在共有している電力源との代替について、どういうふうにお考えなのかということがお伺いできればと思います。
2点目は、今計画されているところには、既設の風力発電や計画中のものがたくさんあるように見受けられますが、電力供給だけではなくて環境への総合的な、他事業との関係というのはどういうふうにお考えかというのもお聞かせいただきたいと思います。その理由として、先ほどもいろいろ出てきておりますが、渡りのルートや動植物の出現頻度が高いような領域や共同漁業権が発生しているところにわざわざ設置するようにも感じられますので、今後いろいろ検討されるということでしょうが、こういう影響の高いところは極力避けて設置される予定なのか教えてください。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
では、事業者のほうからの回答を頂戴いたします。
(事業者)
はい。まず第1点目の旧事業と本事業の違いという点で回答させていただきます。
旧事業と本事業の違いですが、旧事業は、風車の設置方法を着床式としておりまして、その発電所の出力規模を9,900キロワットとして計画をして進めておりました。一方で、近年のコロナであったり、中東情勢、ロシア、ウクライナの情勢を含む円安の影響、人件費や物価高騰の影響により旧事業の方式、規模感による採算性が悪化したということが旧事業を廃止した要因として挙げられます。また、洋上風力発電事業に関する法整備、ガイドラインの整備が進んでいく中で、本件のように、自治体条例による海域占用許可を取得して実施する洋上風力発電所については、その出力規模を、30,000キロワット以下を目安にするということが示されました。これを受けて、私どもといたしましては、使用する発電機自体の出力、並びに発電所全体の規模を見直すことで一定の採算性を確保できる見通しとなりましたので、本事業を計画しているところでございます。
合わせまして、本事業は旧事業を廃止した後に、新たに洋上風力を設置する計画でありますが、旧事業と同様に、再生可能エネルギーの主力電源化に貢献することを目的としておりまして、北九州市における再生可能エネルギーの地産地消実現に寄与することができればというふうに考えております。エネルギーの代替という言葉がございましたが、再エネの主力電源化という形で再エネの比率を高めていくという流れがある中での本事業を計画しているというところでございます。
(北沢委員)
よろしければ何か具体的な、既存のものとの代替というようなことはあるのでしょうか。
(事業者)
例えば「現在の火力発電を廃止して」というようなことでしょうか。
(北沢委員)
はい。そのあたり知りませんので、情報等ありましたらお聞かせください。
(事業者)
私たちの意図で、「この洋上風力を導入するから何かの発電所を廃止する」ということは、計画の中にはございません。今回、第7次のエネルギー基本計画が出たと思いますが、風力発電のいわゆるエネルギー構成の比率を上げていこうというような日本国内全体での動きの中で我々も浮体式洋上風力の開発をしており、その社会実装をより早く実現するため、という意味も含めて今回の事業計画をしているということでございます。具体的に何かの発電所に代替するということではございません。
(北沢委員)
承知いたしました。
(楠田会長)
はい。どうもありがとうございます。
北沢委員、追加のご発言はございませんか。
(北沢委員)
後半のほうですが、他の発電所の既設の風力発電とこれから計画されるものがたくさんあろうかと思いますので、計画されるものとの関係というのはどのようにお考えですか。環境への影響がおそらくもっと増えると思うのですが。
(事業者)
はい。お答えいたします。
今、委員がおっしゃられたように、他の発電事業者も周辺に計画中であります。そのため、今回の手続きにつきましては他の事業者との情報交換に努めまして、可能であれば環境への累積的な影響についても検討していきたいという所存でございます。
以上です。
(北沢委員)
よろしくお願いします。
はい。私のほうからは以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それでは村瀬委員、お願いいたします。
(村瀬委員)
はい。それでは私の方からは大きく2点ございます。
まず1つ目、藻場についてですが、藻場調査の結果で優占したツルアラメそれからウスバノコギリモクという海藻の名前が出ていましたが、これは藻場を作る海藻で、砂まじりの転石や礫上であれば、水深約30メートルまで生育することが可能です。本事業の浮体式洋上風力発電機を海底に固定させるためのアンカーやシンカーなどを設置する際や、発電機とアンカーをつなぐときにおそらくチェーンなどが使われるのではないかと思うのですが、そういったものが海底を削るというか、擦る現象などに対して、海底に生育している海藻や水産上有用な動物も含めた底生生物の生息への配慮をする必要があるのではないかということです。
また、検討中とされている送電線についても、今後の予定でどのように敷設されるかわかりませんが、この海底ケーブルのルートや陸揚げ地点で着生する海藻や藻場あるいは付着動物に配慮する必要があるのではないかということについてお聞きしたいと思います。
(楠田会長)
はい。事業者の方からの回答をお願いいたします。
(事業者)
はい、承知いたしました。
事業計画の方は、詳細は未定でありますが、ご指摘の通り、事業エリアによってはアンカー等の設置に伴う海藻等への影響の可能性も考えられます。今後の事業計画によりますが、影響が想定される場合には、海藻や底生生物について、評価項目として影響を検討して参りたいと考えております。
また同様に海底ケーブルの敷設ルートや陸揚げ地点についても同様に、今後の事業計画によりますが、影響が想定される場合には、海藻、藻場、付着動物についても、評価項目として影響を検討して参りたいと考えております。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
村瀬委員、よろしいですか。
(村瀬委員)
承知しました。
(楠田会長)
はい。続きお願いいたします。
(村瀬委員)
はい。次はカナガシラとスナメリで、評価対象にされた種なのですが、カナガシラは絶滅危惧種と判断されていますが、漁業対象種でもあります。それから事業想定区域は共同漁業権が設定されている海域であることから、先ほどの岩松委員もおっしゃいましたが、漁業者へのヒアリングによるカナガシラの漁獲情報の収集や、あるいはその他の有用水産魚介類の漁獲情報を蓄積して、評価してはいかがかということです。
また、事業実施にあたって、地元の漁業協同組合に丁寧に説明して、理解を得ておく必要があるかと思います。
次にスナメリの生息分布などは、今後必要に応じて実施する現地調査においては、最近の行動様式の知見、例えば昼と夜の生息状況の違いや、単独性か群居性かというようなこともあるので、そういった項目も配慮して調査されたらいかがかというご提案です。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それではご回答お願いいたします。
(事業者)
はい。
2つ目のご意見ですが、ご指摘の通り、カナガシラにつきましては、水産庁により絶滅危惧種に指定されている一方、有用水産魚類として漁獲されておりますので、今後公表されている資料とともに、ヒアリング等を実施しまして、漁獲情報の収集に努めて参りたいと考えております。また、事業実施に当たりましては地元の漁業関係者との協議の中で、丁寧に説明を行いまして、理解を得て進めて参りたいと考えております。
スナメリにつきましては、現地調査を実施する場合には、ご提示いただいたようなスナメリの行動様式に関する最近の知見を参考にしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。以上です。
(楠田会長)
はい。
村瀬委員、よろしいですか。
(村瀬委員)
はい。承知しました。よろしくお願いします。
(楠田会長)
はい。どうもありがとうございます。
それでは、事前にいただきましたご意見につきましては、回答を頂戴いたしましたので、今日委員会に出席されておられます委員の皆様方からご意見、ご質問がございましたら頂戴いたします。ございましたら、リアクションボタンの挙手ボタンを押してください。
それでは藍川委員お願いいたします。
(藍川委員)
ありがとうございます。
まだ計画段階で計画の具体性がない中だと思いますので、今後進めていかれる中で、考慮いただければと思うことを申し上げさせていただきます。
風力発電設備の構造物を組み立てる場所までをどういうルートで運んでこられるのかわかりませんが、仮に陸上ルートで運んでこられるのだとすれば、どれぐらいの大きさのものを、どういう頻度で、どの時間帯に陸上ルートで運ぶかという点について、大気汚染の観点から、できるだけ交通の集中する時間帯を避けるなどの形で、大気汚染物質の排出が抑えられるような工夫をしてスムーズに陸上ルートで運んでいただいて、組み立てて海上で輸送するというようなことを検討いただければと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それでは、事業者の方からの回答を頂戴いたします。
(事業者)
まだ現時点では計画段階ということにはなりますが、一般的に、洋上風力事業の場合は、風車、浮体ともに、海上輸送がメインとなっております。とはいえ、一部陸上の開閉設備等は、陸上輸送を使用することも考えられますので、そういったところにつきましては、ご指摘の通り、具体的にどうすれば影響がないかというのを引き続き検討して、必要であれば、今度の評価の中で反映させていただきたいというふうに思っております。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それでは引き続きまして、田中委員お願いします。
(田中委員)
場所を選定されるにあたってですが、他の候補地などもたくさんあって、それはどちらかというと沿岸側というか白島よりも内側にほとんどが選定されていて、今回は、白島を囲むように反対側に選定されていると思っています。それについて、要は風の向きやいろいろな法律を考えられていると思うのですが、白島一帯が囲まれることによって、白島の地域としての自然の財産というものが何か変わってしまうようなことはないのかというのが1つ疑問点と思いました。
それと今回、記載された事業実施想定区域に限定されていますが、なぜ他の地域が外されたのかというのが知りたいです。候補地として、今、実証機があるあたりなど、いくつか検討されたのでしょうかという2つ質問です。
以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
それでは回答を頂戴いたします。
(事業者)
はい。ご意見ありがとうございました。
対象地域の選定に関してなのですが、少し冒頭に説明したところと被る部分はあるのですが、まず、例えば今、実証機のあるエリアというキーワードが出ましたが、あのエリアは海域の中でも共同漁業権のない一般海域ということになります。つまり、このエリアは自由漁業のエリアということになりまして、この海域を使用しようと思うと、地先の漁協以外の日本全国、例えば北海道の漁業者がイカを獲りにくるというような話があったりもするわけで、そういった方々の了解を取り付けながらしていかなければ、というような非常に壮大な作業になっていきます。一方で今回選定しているエリアにつきましては、共同漁業権というエリアを選定して、事業を計画させていただいております。もちろん漁業との共存共栄ということが前提にはなりますので、漁業者とのしっかりとした協議の中で実施可能かどうかの判断をしていかないといけないのですが、共同漁業権ということで、利害関係者が明確である中で一定の理解のもとに海域の使用同意をいただいて、事業を実施するということを前提に選定をしております。
その前にご質問いただいた、その白島周辺を囲むようにという話に関しては、ご指摘もありましたが、やはり累積的影響ということで、周辺の事業と合わせて地域の環境にどういう影響が出てくるかは、評価の中で我々も検討して、示していかなければいけないと考えております。
(楠田会長)
はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。
それでは、伊藤委員お願いいたします。
(伊藤委員)
1つはバードストライクについて、前も洋上風力で言わせていただいたのですが、この配慮書に出ている確率からすると、例えばミサゴだと10数年に1個体、それからオオミズナギドリだと3年に1個体です。そのくらいの確率というのは、個体数の減少とかそういうことを議論する数には当たらないのではないか。いわゆる「重大な影響はない」というその「重大な」の基準がどこにあるのか。一般的に考えれば、ほとんど影響ないとか、無視できるというレベルになるのではないかという風に思っています。仮にこれが確率10倍になってもそれほどでもないかなという考えです。というのも、ビルのバードストライクという方がはるかに確率高いと昔聞いたことがありまして、基準と比較するなどで、そのあたりの「重大でない」や、「影響がある」、「ない」などを判断する基準があるのかどうかというのをお伺いしたいというのが1点です。
もう1つ、いつもこの洋上風力の時に気になるのは、これが何らかの台風や、あるいは航空機が衝突するなどの形で倒壊したときに、風車を回収できるのかどうかです。もう海の中に沈んでしまったらなかなか回収するのは難しいと思いますが、そのあたりについて、環境影響評価とは関係ないかもしれませんが、見解お伺いできればと思います。
(楠田会長)
はい、それではご回答お願いいたします。
(事業者)
では最初のご質問、重大な影響の程度についてですが、ご指摘の通り、この重大な影響についての判定基準というか、数値基準というのはなく、そういう定量的に根拠を示すということは難しいところでございます。ただ一方で、経産省から出されている発電所に係る環境影響評価の手引きなどによれば、重大の影響というのは、「環境保全措置を講じることで影響を回避低減が可能であると考えられる場合には、重大な影響としては取り扱わない」ということが明記されておりますので、今回は、今後、環境保全措置を検討していった場合、十分回避低減ができると我々は考えており、重大な影響はないという判断をさせていただきました。
続いて2点目の浮体式洋上風力が何かしら事故等で沈没した場合に回収できるかというご質問ですが、まずこの浮体式洋上風力発電というシステムなのですが、浮体は船として認証を進めて参ります。これと日本海事協会の認証を取得して運用していくものになりますので、一般的には船同様、通常の利用に関しては問題ないことは確認されているものになります。一方で、何かしら他の船舶がぶつかって、沈没、倒壊するようなことがあった場合には、基本的には、沈没した船同様に回収するということが前提になってきます。とても深い海域で回収できるようなエリアではないなど、そういった場合には断念しなければならないのですが、現地の海域は水深35メートルとか40メートルくらいの海域ではありますので、技術的には回収が可能ではないかと思っております。
以上でございます。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
伊藤委員よろしいでしょうか。
(伊藤委員)
はい。結構です。どうもありがとうございました。
(楠田会長)
はい。それでは岩松委員お願いいたします。
(岩松委員)
はい。よろしくお願いします。
伊藤委員の質問と似ているのですが、例えば、地震による津波ですとか、台風の大型のものが予測された場合に、風車そのものの物理的影響をどのように予測されておられるのか、または電力供給の面でどのような変化が想定されるのかというところをお尋ねしたいと思いました。
(楠田会長)
はい。ありがとうございました。
それでは、事業者からの回答を頂戴いたします。
(事業者)
ありがとうございます。
浮体式洋上風力発電は、実際に運用するに当たりまして、先ほど日本海事協会の認証というのがありましたが、ウィンドファーム認証というまた別の認証を取ることになっております。その中でサイト条件評価という項目があるのですが、この風車を設置する海域の風況、地震の影響、最大の波高、津波の想定などを50年再現値や100年再現値という、過去の推計と今後の予測からいわゆる環境条件を設定した上で、それに耐えうる設計をするようにしておりますので、基本的には、その認証を通過したものに関しては、現地の環境状況に適応したシステムになっていると理解しております。
続いて、台風等の際の発電した電気の取り扱いなのですが、基本的に風車というのは、我々が想定している風車に関しては、風速3メートルから動きはじめまして、風速25メートルを超えると風車を停止するようにしております。風速25メートル以上の場合は風車のブレードの損傷等の可能性が出てきますので、基本的にはそこでブレーキをかけて、ロックをさせて、今度は暴風待機という状況で発電も控える設定になっております。世の中の一般的な大型風車は、大体そのような運用になっております。その環境条件を超える場合、風速25メートル以上の風が吹く場合には、発電を停止するということになります。
以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。
他にご発言ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それではご発言ございませんので、これをもちまして、(仮称)北九州市白島沖浮体式洋上風力発電事業計画段階環境配慮書の審査を終了させていただきます。
このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。