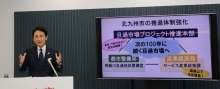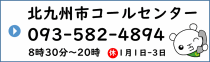|
コメント項目 |
なし |
月日: |
|---|---|---|
| 発表項目 | ||
| 出席者 | 北九州市長 |
4.令和7年(2025年)5月15日北九州市長定例記者会見
【発表案件】
(1)旦過市場再整備に関する体制強化
(2)小倉城・小倉城庭園 入場者数 過去最高
(3)北九アキサポ第1号の指定
(4)下水道管の全国特別重点調査の着手
会見の動画(YouTube)
会見録
(1)旦過市場再整備に関する体制強化

市長
それでは皆さんおはようございます。今日ちょっといつもより多いかな。そんなこともない?今日は何か少し引いていますよね、椅子がね。本当に先週からいろいろ動きありますけど。ちょっと関係ないことかもしれませんが、私厚労省なので少し気になっているのが、出産費用の無償化の話って今話題になっていますよね。少子化対策はずっと私も子育て支援とか政策とかやっていましたけど、なかなか今制度設計するのも難渋している感じがあって、やはりこの保険システムの中で、この出産をそれでカバーするかどうかで結構昔から議論がありまして、ただ「保険事故じゃないので保険の領域じゃないよね」っていうような議論がベースにありながら、そのあと「少子化対策」という意味でその負担をなくしていこうという流れに今なってきていて、っていうことなんですが、ただ他方であれを無償化すると標準的な価格が設定されると。保険でカバーされるっていうのはこれいいことでもありますが、他方で供給するほうにとってはその価格の中で納めないといけないというようなこともあって、保険に入ると上乗せで勝手に取れないですから、追加料金って取れない仕組みですよね。だからそういった中で、今7%ぐらいの産科の方がこれ入ってくるともうやめるかもしれないとかっていう話も出てきている。ただでさえ少子化で非常にそのサービスの提供の対象が減ってきている中で、そういった部分もしっかり考えていかないといけないので。何か無償化するから全部タダになるっていうような図式だけで考えるというのはなかなか制度設計上難しいんじゃないかなと思いますし、もちろん出産の負担を公的に支援するという方向性は、それ自体はいいと思います。ただその制度設計を単にもう無償化ありきで全部やってしまうと、非常にその需給の体制というのが壊れてしまうんじゃないか。これ高校の無償化の時も私は違和感ありましたけれども、やはりその部分をしっかり設計しなきゃいけないというふうに思いますね、この社会保険制度をやっていた者として。ただ私が違和感あるのはこれも個人的な思いなんですが、そもそも少子化対策の本丸が出産の無償化なのかっていう思いもありますね。ちゃんと払えるような世の中にするっていうことが本筋じゃないかと。「子どもの産む数が少ない、だから産むのをタダにする、そしたら産んでくれるでしょう」って、そういうことじゃないでしょうっていう。それはやっていいんですよ、公的な努力で負担を下げていくというのはやっていいんですが、ただ何か出産が減ったから出産を無料にすれば出産が増えるってそう簡単な話じゃないですよね。むしろ個人的にはやっぱり非正規の問題、これが、やっぱり非正規労働者がどんどん増えてきたことと少子化の進展というのはやっぱり分かち難く関わっているというふうに思います。特に若い20代、30代の男性・女性とか言うと男性でも30%ぐらいですからね、女性でも50%以上が非正規っていう状況も、「非正規」っていう呼び方が私あんまり気に入らないんですけれども、そういうようなこの構造的な部分をしっかりアプローチしないと、何か分かりやすい、あるいは直接的にロジックが見えやすい部分を何か無償化するとか、そういう見えやすいとか、何て言うんですかね、伝えやすい形で少子化対策ということをやるっていうことではもう簡単にはそう変わらないと。やっぱりしっかり稼いでしっかり払えるっていう状態をつくるということが大事かなというふうに個人的には思っています。また国際的に見たら、その住宅の可処分面積と子どもの数で結構リンクしているんですよ。やっぱり2人目、3人目を考える時に、やっぱり住宅に部屋がないとか面積が少ないとかってものすごく制約になっていると、心理的に。直接じゃなくても間接的にものすごい制約になっていると思うんですよね、そういう論点もしっかり考えていかないと。あとやっぱり狭い住宅だと夜の営みもしづらいとかいうような観点もあります。やはり住宅政策にも関係することだし、何かそういう論点も含めて少子化対策って正面から向き合っていかないと、何かあの無償化だけに限局した、そこがバーッと議論の焦点になっていくということで。あれ自体難しいと思いますし、やっぱりそこは私は違和感を感じるなというのは、ちょっと厚労省出身者としての思いということで少し今日のアイスブレイクとして話しましたけどね。ちょっとそんなことも皆さんどう思われるでしょうかね。今日それは全然本筋の発表と違うんですが、今日もちょっと発表事項たくさんありますので、少しお時間頂戴しますけれども、お話しをさせていただきたいと思います。
発表案件いくつかありまして、まず旦過市場の再整備についてでございます。こちら、旦過市場の再整備。これは「北九州(市)の台所」として大事な意味合い、あるいは機能を持つこの旦過市場、長年市民の皆さんから愛される場所として今も非常に大きな存在感を持っているところ、これは大切な場所です。この地域の旦過市場に関しては、もうとにかくキーワードは「安全」です。今の再整備がスタートしたのも、そして今もやはり安全を確保するということが第一の理由になっております。水害や、神嶽川増水して危ないこの水害、そしてこの火災もありますしね。「安全」という意味でのいろんな課題を抱えている現状、やっぱりそれを乗り越えていこうということでこのプロジェクト始まっているわけです。様々な危険、その課題を払拭をして「安全な市場」「魅力的な市場」をつくるという大目標に向かって、官民一体となって様々な課題を越えてきた歴史があります。そうした意味で、さらにこれを「安全な市場」、そして「魅力的な市場」、これをつくっていく、そこに向かって進まなければならないと。もう申し上げるまでもありませんが、火災や浸水、様々なものがありまして、その中で市内外の皆様からの温かいご支援もいただきましたし、レンガ広場の整備、販促イベント等々、旦過市場関係者の皆様による、あるいは多くの皆様の思いによる今賑わいを取り戻す、そして賑わいをさらに増やしていくという取組行われているということでございます。他方、こうした中で「再整備のアップグレードの検討」というのもやってきました。市場の関係者の皆様、あるいは学生の皆様なども交えて、30回以上に渡って話し合いが行われてきました。次の100年に向けて、「食」や「人」をキーワードとして、どんな旦過市場になっていくべきかということで、今年の3月末で一定この議論に区切りが付いたという状況でもあります。他方で今の市政の中においても「観光大都市への進化」「世界をリードするサステナブルシティ」といった辺りも私たちのキーテーマとして掲げていると、こういう流れ、あるいは時の流れ、動きというものがある状態にあります。そうした中、こういったビジョンに関する、アップグレードに関する検討も様々な方としていただいたり、あるいは市政の方向性、こういったところで、やはり「安全な市場」「魅力的な市場」、これをつくっていく、そのために官民一体となって課題を乗り越えていく、これが必要なわけでございます。そのためにやはり私たち、状況変化しています。もう状況も変化している、やっぱり工事っていうのは、再整備というのは、やっていく中でまた見えてくる課題ってもうこれは万博も何もそうですけれども、やっていく中で見えてくる課題、あるいは波というものがある。こういった中で私たちもしっかりと官民一体となって取組を進めていく。もちろん官の側でも努力をしていくということは必要なことです。そこで推進体制もさらに強化をしていきたいと考えています。「旦過市場プロジェクト推進本部」を設置いたします。片山副市長をトップ、本部長としまして部局横断的な体制を強化します。この中では、都市整備局、産業経済局、そして関係する方々に入っていただいて強力な推進体制、もう一段ギアを上げて旦過市場への取組を進めていきたいと考えております。大丈夫ですか、梅本さん写真大丈夫ですか。もう1回戻りましょうか。
記者(西日本新聞)
いいです、大丈夫です。
市長
いいですか、はい。推進本部のメンバーですけれども、ご覧のとおり10名で、ハード面での整備が本格化してきました。先ほどアップグレードの議論、一定ひと区切り付いたということもありましたし、市政の方向性というのもありますし、またハードの整備がより本格化してきました。また整備後を見据えて、運営面やプロモーション面での取組の強化ということもより画素数を上げていく必要があります。こういった中で「旦過市場」、「安全」、そして「魅力的」、こういうところに、大目標に向かってしっかりと行政としても体制を整えていきたいというふうに考えております。そして組織横断的にやっていく、ここも大事なところであります。従って、こういった関係局長、もうたくさんいますね。いろんな方が入って、しっかりもう「オール北九州市」で官側の努力をしていくということでございます。このあと11時30分から推進本部の第1回会合を開催をいたします。こちらにも冒頭ご取材いただけるということになっていると伺っておりますので、お願いをいたしたいと思います。事業は工事中も市場の営業を継続できるよう4つのエリアに分けて段階的に整備をしていく。そして、安全のために始まった再整備ですから安全に行わなければいけません。どうやって安全を確保しながら、慎重に丁寧にこの一歩一歩を進めていきたい。河川上の建物解体、河川改修工事などを行っていきたいと考えております。現状、今日、また今後、推進本部でもしっかり共有しながら、あと市場の皆さんとも共有しながらということになりますが、既に既報のメディアの方もおられますけれども、今現在の情報を、今立ち位置を見ていきますと、昨年度、整備する建物や河川上の建物の解体などについての専門業者による基本設計を行いました。その結果、安全な、まずこの上のほうですけどね、「安全な市場」をつくるという大目標に向かって、安全性を最優先にして必要な工事手法を採用するためには、十分なリードタイム、施工時間が必要だということが分かってきました。そうしたことで事業期間をしっかり取って、事業期間の延伸の可能性、これが出てきたということが1つ現状としてございます。これ工事期間が当初の約1年から、市場と大学が共同で整備するBC地区の建物ですね、工事期間が当初の約1年から約1年8ヶ月が必要になるというような可能性が出てきたと聞いております。私も文系なのでそんなに詳しくはないんですけれども、BC地区のこの建物が長屋形式で並んでいて、そこに梁がビューッと入っていって、その梁を自動で、どんどん機械で壊していくっていうことをやる予定だったんですが、そこをドーンと自動でやっていくとその振動で、こちら側のここをドーンとやるとこちら側の建物が、店舗が崩壊、壊れてしまうんじゃないかと、梁が壊れてしまうんじゃないかということが分かってきたと、実際見ていくと。そこで、それを丁寧に手掘りじゃないですけど、手でもう丁寧に1個1個、慎重に慎重にそろりそろりとこの梁を壊していくということの作業が必要で、これ結構時間がかかるということが分かってきましたので、それが影響しているという報告を受けています。大体その説明で合っていますよね。ここで入ったらちょっと。
担当者(都市整備局 神嶽川旦過地区整備室)
神嶽川旦過地区整備室の草野と申します。今、市長がおっしゃられた1棟の、一連の長屋の形式の建物につきましては、BC地区というのではなく川側ですね、河川上の建物が1棟の長屋形式になっているということでございます。
市長
BC地区じゃなくてその川側の、川にあるこの長屋ところの建物がっていうことですね。ここにドーンと自動でやっていこうというのを、手で丁寧にやっていかなきゃいかんというようなことのようです。詳細はまたあとで聞いていただければ。そんな、やっぱり「安全」です。安全担保、これをしっかりやっていくためにリードタイムを取っていくということです。これはやはり事業の進捗、そもそもの安全のためにやっているわけですから、しっかりとそれを最優先にしていきたいということでご理解賜りたいというふうに思います。また、これはもうあらゆる案件でこのお話しさせていただいておりますが、資材高騰、人件費増、これはもうあらゆる案件でお話をさせていただいておりますけれども、当初想定していた約20億円から39億円になる可能性が出てきているというような状況でございます。こういった今、現時点の立ち位置、こういうような状況の変化、しかし私たちは「安全な市場」をつくる、「魅力的な市場」をつくるという大目標に向かってしなやかに対応していかなければなりません。様々な外部環境の変化、これはありますけれども、やはり官民一体となって旦過市場、「100年続く安全で魅力的な市場」をつくるというところに向かって一緒に課題を乗り越えていきたい、そう考えております。もちろん今後、早急の推進本部などでもいよいよ本格化してきておりますので、しっかりと取り組んで、評価、検討をしっかりしていくということは言うまでもないです。また市場の営業をされている皆様、ご利用されている皆様、そうした方々に無用なご不安、心配が出ないよう、様々なコミュニケーションをしっかり取って丁寧に誠実にこれまでどおり今後も進めていきたいというふうに考えております。あと整備費の増額の可能性に関連して、入居者の家賃に影響するのではないかというご心配の声もあると伺っております。言うまでもなく家賃というのはマーケットにおいて、その不動産の価値に応じて決まっていくものであり、行政である市としてそれを一概に予見するということはできないものでございます。そういう性格のものではございます。ただ、そうした中で今後、資金がネックになってくるとか、そういった場合には市の融資制度、あるいは経営相談などについて専門家が助言させていただくなど、行政としてできること、これはしっかりと皆様に寄り添っていきたいというふうに考えております。いずれにしましても旦過市場、「安全な市場」、そして「魅力的な市場」をつくるという大目標に向かって、官民が一体となって、ともに様々な課題を乗り越えていきたいというふうに考えております。
(2)小倉城・小倉城庭園 入場者数過去最高

市長
次は小倉城についてです。こちら小倉城、令和6年度の入場者数が過去最高を記録しました。北九州市の観光コンテンツ、資源として重要な位置を占める小倉城であります。「観光大都市への進化」、ここに向かって第一歩進んでいこうということ、これも市政のテーマとして掲げている中、小倉城は非常に順調です。小倉城庭園、シンボリックな観光施設でありますから、本当に私たちの大切な財産としてこれからも守り、そして多くの方に親しんでいただきたい、訪れていただきたいと思います。令和6年度、小倉城が29万5,799人、前年度比が14%増ということで、再建直後を除き過去最高を更新しています。小倉城庭園13万2,532人ということで、前年度比23%増ということになりました。開園以来、過去最高を記録をしています。今「日本一おもしろき城」として、エンタメ性も組み入れながら様々な今トライアル、取組をしていただいている、こういったご努力も大きな成果に結び付いているというふうに認識をしております。小倉城の主な取組なんですが、これも皆さんもうご案内のとおりですけれども「寿司&キャッスル」、それから「小倉城のプロレス」、それから「小倉城ドラマッピング」といったような話題性の高いイベントも展開していただいております。いろんな土地に、東京とか他の九州各地に行っても小倉城の話になった時にやはりこういう取組をしているということ、それは話題というか、「こういった取組を小倉城はしている」ということだけでもものすごく注目を浴びるし、「ぜひ行ってみたい」ということを私も言われることが少なくありません。一方、小倉城庭園におきましては、和の趣溢れる空間を活かした企画、これが甘味処のオープンであったりとか、アフタヌーンティーセットの提供であったり、あるいはレーザーライトアップショーとか、これもいろいろなことやっています。庭園ならではの魅力を最大限引き出すということ、これにチャレンジをしていただいているということであります。歴史的な場所、そこに現代的な楽しみ、エンターテインメントを入れていく、これによって新しいステージ、新しい魅力をどんどん発揮している今小倉城、そして庭園だというふうに考えております。

市長
今日少し追加でここも強調しておきたいのが、実は小倉城と庭園は企業誘致や外国、特に海外からの要人をお受け入れする時にものすごく大きな力を発揮しているということです。やはり東京の企業さんのトップの方とか、あるいは海外の要人の方が来られた際、これ全部ここで申し上げられませんけれども、対外的に公表しているものだけでも、例えば先日のインドの州の首相ということもありましたし、あとヤマトさんの写真もありますね、ヤマトの社長の写真ですかね。これはやっぱり、こういう場所っていうのはものすごく力が強いです。北九州市の歴史や、あるいは文化、そして北九州市が目指している市政の方向性、こういったことを体感していただく、本当に強い訴求力があると思っています。そういった意味でも「観光スポット」ということだけじゃなく、私たちが様々市政を進めていく上でも大きな武器になっている、ここも非常に強いところだと思います。都市の顔としての小倉城、そして庭園、この力は今後も磨き、そして活かしていきたいと考えています。もちろんその他にも、北九州市には皿倉山もある門司もある、いろいろあります。企業誘致なんかで言えば歴史的な建造物、例えば三宜楼とか旧松本邸とか、こういったところでお話しさせていただく、これもものすごいインパクトあるんです。だから北九州市の歴史があるからこそ、そして文化があるからこそ未来に向かってのチャレンジができる、これは本当に多くの皆さんのご尽力の賜物であるというふうに改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。今着実に、門司レトロの展望台も着実に増加傾向にありますし、皿倉山のケーブルカー、スロープカーの利用者数も過去最高水準を達成していると聞いております。様々な取組、観光であれビジネスであれ、様々な形でこの力をしっかりと活かしていきたいというふうに思います。
(3)北九アキサポ第1号の指定

市長
次に、空き家対策に関しまして。「北九アキサポ」がスタートをするということになりました。こちらですね、空き家問題。これはもう全国的にも非常に大きな課題となっているし、高齢化先進都市の北九州市でも大きな課題になっているということは皆さん言うまでもありません。ここに対して新たに前進するということの発表です。今、現状見てみますと、平成25年度から令和5年度の住宅総数と空き家の数、これ見ていっていただきますと、一生懸命、今、空き家の発生予防、これを北九州市もずっとやっています。啓発活動もやっていますし、あと流通の促進ということもやってきて、その抑制に一生懸命努めながら、何とかその空き家率というのが激増しないように食い止めてきているというような状況ではございますが、やはり高齢化が進んでいる北九州市、政令指定都市の中でも空き家の比率というのは高い状況にあります。もうこれは皆さんご存知のとおり、やはり所有者が空き家をどう活用したらいいのか、どう管理していいのか、誰に相談していいのかそこら辺の「どうしたらいいのかが分からない」という課題がまず根底に横たわっております。そして、そうした場合に区役所とか行政にご連絡いただくのですが、私たちも不動産流通のプロというわけでは必ずしもないので、もちろん「こういうことも考えられる」、あるいは、「こういうようなところに相談しては」とかっていう時には情報を集めてご回答をするのですが、やはり行政としても体制、あるいはノウハウに限界があるという、こういうような状況、すなわち入口の部分で空き家というのは非常に問題というのは壁がある、こういう特筆があるわけでございます。今後も空き家は増加するという中で、これに対して対処していかなければいけない。そこで今、1つ官民連携でしっかり課題を解決していこうという動きが出始めております。それが令和5年の12月の「空家等管理活用支援法人制度」というのが立法されまして、そこでまたそれを受けてのガイドライン、その指定方針というのが今年の3月末、年度末に明らかになりました。国土交通省から。こういった国のほうでも「官民一体となってやっていこう」、「空き家問題は国家的な課題の1つだ」という認識を強めてきています。そうした中で、「北九州市空家等管理活用支援法人」、「北九アキサポ」というのをスタートさせたいと思います。法律上の名前は難しいのですがもう北九アキサポ、空き家サポート、アキサポと、北九アキサポというふうに。「北九州市空き家なんでもサポーター」というのが正式名称ということでなっておりますけれども、「北九アキサポ」ということでスタートしていきたいと思います。市民の皆様が抱える悩みは管理や活用・売却・解体そして相続税制など本当に広いんです。空き家に関して。こういった中で北九アキサポはその法人が持つノウハウや専門性をもちろん活用していくとともに、様々な相談・管理していくとともに、ワンストップ、この大事なことは専門家と連携をして、「ワンストップ」そして「専門的な助言」、「ワンストップで専門的な助言」、これが行えるというところに価値の中核があります。先ほど申し上げたように、空き家を抱えていらっしゃる方が、どこにどういう相談をしていいのか、何から考えていいのか、これが分からないということが大きな壁になっていました。ワンストップ、しかも専門家の方と連携しながら答えていくそれも出来る限り迅速に答えていく、ここがポイントです。私、福祉の世界とか社会福祉の世界いましたけど、昔というか、今、地域包括支援センターというのがありますけどもね、かつてはもうそれぞれの部局が福祉部局・医療部局・障害部局・何とか部局って全部分かれて役所に全部相談行ってそこでやっていくので縦割りで情報が集約されないし、その人を中心に考えることができないということで地域包括支援センターっていう、包括してサポートするっていう仕組み、これ大きな変化だったんですけれども、そんなイメージで空き家についても今までいろんな方に相談していたのを一気にやっていくというような体制を北九州市が組んでいくということです。

市長
具体的な、これは県内で初めての指定となります。「北九アキサポ第1号」ということで、「全日本不動産協会」様を指定をさせていただくことになりました。こちらで今までご尽力、空き家問題へのノウハウも蓄積されておられるこの協会さんをサポートさせていただきました。もう今申し上げましたように、5月19日から個別無料相談がスタートをいたします。もちろん出前のセミナーこういったものも行っていただきます。イメージここ見ていただきますと、市民の皆さんが今までは「どうしたらいいのかな」ということで、「困ったら行政に連絡しようかな」ということが多かったんですが、これからは北九アキサポのほうに相談をいただくと、もちろん行政とも連携をいたしますが、大事なことこの下のところですね。専門家との連携です。行政書士、司法書士、弁護士、建設業、税理士、金融機関こういった様々いろんなさっき課題があると申し上げましたが、こういったところと連携をしながら回答をしていくというこういう流れになっていきます。ワンストップで専門家の助言が受けられる。これによって空き家問題を動かしていく。こういうような流れになっていきます。まさに総合的ワンストップな体制がとられていることでございます。5月19日からということでございますが、すみませんね、その次のページにありましたね、もうちょっと具体的にありました。空き家の所有者、活用希望者の方がこういうふうに相談をして回答していくというようなことで、解決策を提示していくという、より伴走型の支援に近づいていくというようなことであります。こちらですね。5月19日相談受け付け開始です。専用ナビダイヤルも設定をされておりますので、市民の皆様ぜひこれをご活用いただきたいと思います。福岡県で初めてこの指定をさせていただいた、この法人北九アキサポ、ぜひご活用いただきたいというふうに思います。
(4)下水道管の全国特別重点調査

市長
次は、「下水道管の全国特別重点調査」であります。北九州市では、市民の皆様の安全安心を確保するため、定期的に下水道の点検を行ってきているわけでございますけども、「下水道管の全国特別重点調査」、これが5月30日にスタートいたします。これを発表させていただきます。少し振り返りますと、1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没事故を受けまして、3月18日に国土交通省が全国の自治体に対しまして、「下水道管の全国特別重点調査」の実施を要請しました。この件につきまして北九州市は5月30日から調査を行います。実は道路の陥没事故を受けまして、北九州市では、直径2メートル以上の一部の下水道管を対象に、地中レーダーを活用した独自の点検というのを2月上旬から4月下旬まで実施をしてまいりました。今のところ下水道管の破損に起因する空洞は確認をされていません。今回、国の動きも受けまして、これ縦軸が耐用年数、発生しやすさこういった事故の、そしてこちら管径、管の太さ、これが事故時の影響の大きさということを見ていただくと、今回、全国の特別重点調査に入ってくるのが、この管径が2メートル以上、そして古さが30年以上というものが対象になってきます。こういった一番リスクが高いと思われるところ、そして影響が強いというふうに思われるところに、国が重点調査していこうという要請をしてきたわけです。このうち、ちなみに、54キロメートルこの赤いオレンジの優先実施。こっちはもう夏頃までに実施をしていく。そしてこれが3キロメートルぐらいあります。そして、その黄色い部分、そしてこれが1年以内を目途に実施していこうと、この部分が54キロございます。こういったちょっと優先順位、2段階ありますけれども、こういった部分について、私ども特別重点調査を行っていくというようなことです。調査方法は、調査員がマンホールから下水道管に下る「目視調査」、そしてもう1つ「ドローン調査」、こういったものを併用し、管の健全度を確認するということになっております。ドローン調査につきましては、浄化センターに接続する水量が多いところ、そこは人がなかなか入りづらい。あるいは硫化水素濃度が高く、そういったいろんなガスが出ているというようなことで、目視での調査が困難な箇所の調査にはこういったドローンを使っているということになります。今回調査で、私たちドローンを使ってまいります。これは八潮市の道路陥没現場で使用されたものと同一機体でございますけれども、実はこのドローンによるこの機体を全国重点調査で使用するというのは、全国で北九州市が最初になります。これはメーカーさんの確認したところ、この機体の活用というのは私たちが先陣をきって行っていきたいというふうに思います。ドローン、これなんですけど。これが、この八潮市でも使いまして、今度私たちが初めて扱っていくという、ドローン調査のドローンでございます。こちらですね。何で私がこのドローンをそんなに恐る恐る、いつになく持っているかというと、900万円です。ということで、これは私たち買ったわけではありません。これは借りているというかリースになるわけですけれども、これ900万円ということなので、間違っても落としたり、踏んだりしないようにしないといけないということが、事前にありましたもので、このドローンを使っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。なので、こういったものも使いながらドローン点検をしていくということでございます。ちょっとどんなふうにドローンが動いていくのかそのイメージを持っていただくために、ちょっと動画見ていただいて、ドローンを活用した点検状況です。
(動画視聴)

市長
こうやって見ていただきますと、これドローンが進んでいくわけですね。下水管の中をこう見ている。こうドローンがこう入っていってこう動いているところですよね。これ40年経ったらこんな感じのようです。こういくと、このマンホールのところにやってきましたらこの滝にドローンが奪われないのかという心配になりますけど。このマンホールのところにこう、今上がっていっている模様ですね。ドローンがこう来て、こう落ちているところ、マンホールのほうに上がっていくと。ここにドローンの巣がありますので、ここにドローンがこう戻っていくという、着陸5秒前。ここにドローンが入りまして、これで帰りましたということでそれで引き上げて、マンホールから引き上げていくとこういうような調査をしていくと、これを一部水量が多いところとかそういうところで使っていくというところでございます。こういった、新技術の活用というのもやっぱりやっていきたいと思います。本格的に私たちもこのドローン点検というのも導入しながら、下水道管のメンテナンス、DXを進めていくと。そしてリスクを限りなくゼロに進めるための取組、これを加速していきたいというふうに考えております。私から以上でございます。それでは、ご質問を承りたいと存じます。
(5)質疑応答
記者(読売新聞)
幹事社の読売新聞の梅野です。まずは、旦過市場なんですけれども。新しい新チームが本日から始動するということで、改めてこのハード、ソフト両面を一体的に捉え、ギアを上げて取り組むのが目的ということなんですけれども、今後の具体的な目標を、こういったことを達成したい、そういったことがあれば教えていただけますでしょうか。
市長
そうですね。先ほど申し上げたとおり、安全な市場、魅力的な市場をつくるという大目標に向かって、官民一体となって様々な課題を乗り越えていく。これが大切なことです。行政としても、より体制を強化をして、安全な市場、魅力的な市場をつくるために、これまで地元でも様々行われてきたご議論、こういったものもしっかりと踏まえ、様々な課題、現状認識を共有し、それを乗り越えていくということをやっていく。そして市場の皆様にもしっかり寄り添って進めていく。こういう推進役として、本部の機能を発揮させていきたいというふうに思います。具体的な旦過像については、もちろんもうまずは安全をしっかり確保していくということが大事でありますけれども、その他より多くの市民の皆様が安心して使える、そしてこれからも100年続くような市場をつくっていこうという言い方ありますけれども、多くの方が、次の世代にもしっかりと旦過市場を引き継いでいける、そして多くの方が訪れていただける、そういうような市場をつくっていきたいというふうに思っております。
記者(読売新聞)
続きまして、小倉城と小倉城庭園の来場者数が過去最高を記録したという経緯なんですけれども。こちらにつきまして、いろんな取組をされていらっしゃるということではあるんですけれども、今回その過去最高を記録したその背景として、どういったことが考えられるのかっていうのをお伺いできますか。
市長
斬新で独自性の高い取組を積み重ねてきたということは大きな要因だと思います。やはり寿司&キャッスルであったり、天守閣での食事だったりプロレスだったり、ドラマッピングだったり、甘味処だったりアフタヌーンティーだったり、もういろんなことを、今とにかく「日本一おもしろき城」にするというコンセプトを明確に持って、そこで様々な手を打ってきたということが1つ大きな要因ではないかと思います。もちろん底辺としてもう1つ、インバウンドというのも全体としての大きな流れというのはある。そういう部分もあるかとは思います。今、城が2割、庭園が3割ですかね、インバウンドがね。そのぐらいを占めています。なので、なんか今年4月から多言語のオンラインチケットというのも導入しておりますしね、さらにインバウンドの取組も期待をしていきたいというふうに思っております。はい。
記者(読売新聞)
北九アキサポの指定についてお伺いします。今回第1号指定法人に選ばれた、全日本不動産協会なんですけれども、こちらを選ばれた理由、ノウハウを持っていらっしゃるということではあると思うんですけれども。なぜここを選ばれたのかっていうのを伺いたいのと、あとこの全日本不動産協会が、北九州市以外でこういった、その指定の実績が、どの程度ある団体なのかっていうのが分かれば教えてください。
市長
はい。全日本不動産協会さん、一言で言うともうノウハウが集積していると、空き家に非常にこれまで積極的に取り組まれてこられた、一言で言うとそういうことでございます。空き家の相談・情報提供・管理・活用・普及啓発・活用管理等々、そしてこの協会様は宅建の宅地建物取引士や1級建築士、土地家屋調査士などが所属をされておりまして、もう様々な専門家との連携体制がしっかり組まれているということで、相談される方が希望する売却・購入・賃貸・維持管理などのテーマに関しまして即時適切に対応できるということが強みだというふうに考えております。この協会さんが他の自治体の指定を受けたかどうかっていうのは把握していますか。
担当者(都市戦略局 空き家活用推進課)
都市戦略局空き家活用推進課長の秋山です。よろしくお願いいたします。全日本不動産協会さんにつきましては全国に支部がありまして、他都市でも指定を受けているといった状況です。数についてはちょっと把握はしてないんですけども、こういった活用支援法人をやっていくといった都市について、手を挙げていくと、全国的に広げていきたいというふうなことを聞いております。1点補足なんですけれども、先ほど全日不動産をなぜ指定したかといったお話があったんですけども、市のほうが支援方針を指定するための方針を示しております。その方針を見て、各法人さんが、「ぜひやりたい」といった申請をしていただいて、私ども審査して、この法人さんであれば問題ないといったことで指定させていただいております。以上です。
記者(読売新聞)
ありがとうございました。幹事社からは以上です。
市長
はい、山下さん。
記者(毎日新聞)
毎日新聞山下です。旦過市場に関してお伺いします。工期の遅れということで1年8ヶ月程度の遅れBC地区ってありましたが、まずBC地区とそれの連なるBE地区こちらがその工期の遅れによって懸念されることですとか、ちょっと改めて遅れることによって市が、市場関係者に対して新たに支援をしないといけないようなことどういうことがあるか、懸念も含めて教えてください。
市長
今回、事業期間が延びるということについて、やっぱり安全担保に必要な工事手法を採用しなければいけない。安全が第一であります。従って、そこのところに関しまして13日には、旦過市場の商業協同組合の総会。あるいは、14日に旦過市場で営業されている皆さんへの説明、個別説明ということをさせていただきました。そのことに関しましては、安全担保に必要な工事手法を採用することにより、事業期間を延伸する可能性があるということは、「建物が安全に長く使用できるものであってほしい」といったご意見をいただくなど、多くの皆様から、概ねご理解をいただいたというふうに考えております。このあと市の体制強化についても、やはり「にぎわいづくり、まちづくりに対して積極的に市が関わってくれるということはありがたい」といったようなご意見もいただいております。多くの方からもご理解今いただいているというふうに認識をしておりますので、今後もしっかりコミュニケーションをとって進めていきたいというふうに考えております。
記者(毎日新聞)
BC地区に関しては市立大の新学部の設置というものが期限迫っているわけですが、もうちょっと間に合わないかもしれないという現状ですけれども、募集も含めて、どんな影響がありますか。
市長
今回、やはり安全が一番最優先ですので、安全な工事をしなければいけないということを最優先、そこは大学のほうにもご理解いただきたいというふうに思います。ただ、大学のほうでそういった検討する中で、やはり当面は、当面というか1年間はそういった延びた中でもきっちり対応できるという、キャンパスは整えられるというような北方のほうですね。というふうに聞いております。従って、しっかりと未来に向かって、大学も都心部でしっかりと、また市場とも連携しながら学生が育っていくそういう環境をつくっていきたいという思いの中で始まっているプロジェクトですので、しっかりとそこと連携をしながら進めていきたいというふうに思います。ただやはり一番の皆さんの安全が第一ということはご理解をいただいているというように感じております。
記者(毎日新聞)
事業費に関しても増額、かなり2倍近い増額ということで、やはり市立大が得ていた補助金っていうものから大分出てしまう形になると思うんですが、市の負担と言いますか、それは今後どうなっていくんでしょうか。
市長
この物価増・人件費増っていうのはどの事業についても避けられない大きな流れです。やはりそこをどう乗り越えていくのか、全般として、やっぱコストが上がっていく。これはもうどの事業でもあまねく生じている事態です。こういった中で、どういうふうにそれを分かち合っていくのか、これはしっかり相談をしながらやっていく必要があるというふうに思います。そうした中で、それに伴う公費の増というのが、どういうように賄われていくのか。もちろん市としても、大学に委ねるだけではない。やはり設置者になりますから、しっかりとそこは考えていきたいというふうに思います。
記者(毎日新聞)
最後、本格工事が始まったA地区の複合商業施設に関してなんですが、1階66区画ですかね、こちらの例えば入居の見通しですとか、あと2階の活用方法に関して、何か見えてきているものがあるのか、現状があれば教えてください。
市長
そうですね。A地区につきましても、そこの部分のA地区の床をどういうふうに使っていくのか、こういったあたりは関係者の皆さんと今様々な調整をしています。もちろん工事の進捗の中で、それぞれの企業さんのご事情もあるでしょうし、それぞれその事業を取り巻く環境、こういったものも変わっていく中で、どういうような形になっていくのか、そのコミュニケーションというのはかなり頻繁にそして濃密に行っているという状況でございます。それは決まり次第、お知らせしていくということになろうかと思います。
記者(毎日新聞)
分かりました。ありがとうございます。
市長
はい。富﨑さん。
記者(TNC)
TNCの富﨑です。よろしくお願いします。発表案件以外に2つちょっとお伺いしたくて、まず日産さんなんですけれども、国内の苅田町の工場を含む国内の工場も整備統合の範疇に入っていると、対象に入っているという。
市長
苅田の工場の。
記者(TNC)
はい。苅田の工場も含めて国内の工場も統合の対象の中に入っているという話になって、地域にはちょっと不安視する声とかもあります。市長、先週ちょうどバッテリー工場の案件でエスピノーサ社長ともご面談なさったと思うんですが、まずはその日産の今回の大掛かりなリストラ策、地元の市長として、どういった受け止めをなさっているかと、あとは、今後非常に裾野が広い産業でありますから、市内の中小さんとかにも影響が出てくるんじゃないかという感じもあります。どういった支援なりをお考えなのかをまず教えていただけますでしょうか。
市長
はい。日産というグローバル企業が、今非常に経営状態苦境に立たされているということは、様々な数値、業績見込みを見ましても、つまびらかになってきているところです。そうした中で、苅田工場、これは私たち北九州市民も1,000人以上が働いている。また、関連企業も含めれば、少なからぬ市民の皆さんの雇用や生活に直結する課題であるというふうに考えています。こうした中で、やはり苅田工場、これは日産自動車さんのグローバル戦略の中で、非常に重要な位置を占めるものであるということを踏まえた対応がなされること、これを期待したいと思います。もちろん行政として、あるいは経済団体とも連携をしながら、ご相談、あるいは様々なご要望あれば、私たちもしっかりそれは受け取っていきたいと思います。またそれに関して言えば、本当に先日の日産の工場の断念、これは日産自動車というグローバル企業がグローバルの戦略の中で行った判断であり、非常に残念ではありますが、北九州市としては、これまでの未来産業を育てていくという戦略はブレることなく、しっかりと進めていきたいと考えています。やはり、「恐れるより備える」っていうことが大事です。第1弾として先日、企業さんのトランプ危機に対する対応というものの、第1弾の打ち手というのを発表させていただきました。もちろん不確実性がものすごく大きい。ただその中でも、恐れるだけではなくしっかり備えていく、そういったスタンスでやっていきたいというふうに思います。私たち北九州市は、やはり未来産業、次世代モビリティー、半導体、蓄電池などなど、これを軸として、私たちのグリーンの力をしっかりと活用しながらやっていく、そのスタンス、戦略というのは、これからもしっかりと堅持して、個々の案件、それに依存するだけではなくてしっかりとこれからも進めていきたいというふうに考えております。
記者(TNC)
この件に関して社長と面談なさったときに、苅田の工場どうするかとか、恐らくは福岡県も含めて、苅田はもう現在を維持なり、影響がないようにっていうふうなことのお話にも及ばれたかと思うんですが、その際はその苅田工場に関して特段の言及というのは社長のほうからあったのでしょうか。
市長
エスピノーサCEOとお話したとき、私からも、やはり苅田工場による、苅田工場に関する地域経済への影響。これはやはりグローバルな戦略の中でも苅田工場は大事なものであり、しっかりそれを踏まえて対応してもらいたい。そして影響が最小化されるように、私からも申し入れはしました。それにCEOのほうからも、重要な拠点であるというふうにグローバル戦略の中でも、工場、重要な拠点であるとそうした中で、ご懸念は非常に分かるということで、雇用や生産については最大限努力していくというようなお言葉がありました。なので、そういった認識のもと、日産さんのほうでやっておられるということだと思います。
記者(TNC)
話がちょっと変わるんですけども。紫川の下流に架かっている常盤橋、私も何回か取材をさしていただいて、1月に住民と懇話をなさっていて、3月にあり方検討会、その後ちょっと時間が経ちましたけれども、その後の進捗なり、方針なり明示するものとかがあれば教えていただけると。
市長
常盤橋のあり方検討会、3月末に開催をいたしまして、地域の方々や専門家から様々なご意見を伺うことができました。中でも「常盤橋はどのような形であっても残してほしい」、あるいは「木製の橋桁の部分は補修が困難であるということのために、安全性のことを考えるとできるだけ早く撤去すべき」といったご意見出ました。そういった辺りに意見の一致が見られたというふうに聞いています。こうした、私としては検討会での意見をしっかりと受け止め、架け替えを軸に「あり方検討会」で議論を深めていきたいと考えております。一方で、常盤橋は現時点で直ちに落橋するという蓋然性が高いというわけではないんですが、他都市では落橋の事例もあり、そうしたリスクについては十分留意する必要があると考えております。万が一、木製の橋桁が落ちた場合、橋桁が下流へ流れずに沈み、川の流れを堰き止め、水が溢れるおそれがあるというようなことでございます。これは私も技術系の方によく教えてもらったんですが、橋の土台があってその上に木製の橋の部分、橋桁っていうのがドーンと落ちた場合、それがプカプカ浮いて流れていくということではなくて、その橋桁がドーンと落ちた時に川を堰き止めてしまって、そしてそこがダムのようになって、そして水が両側にブワーッと溢れてくるという、こういうリスクがあるそうです。なので、何か私は素人考えで「落ちたら何か流れていって危ないよな」とか思っていたんですけど、そんなことではなくて、落ちたらもうドーンとそれが堰き止めてしまうという、こういうリスクがあるというようなことであります。ですから、本当にこれ落ちた場合というのは、万が一というか今老朽化していますので、落ちた場合にはそういったリスクが発生するということを認識をしてやっていかなければいけないということで、何よりもやはり市民の皆様の安全、これを担保すべく、この木製部分を取り外すとか、そういった部分、何かそういったことがもう万が一にも起きないような対応というのを考えていかなければいけないというふうに考えております。これいいですかね、今の技術的説明は。分かりやすく言えばそういうことです。そういうことですよね。大体いいですかね、それで。
記者(TNC)
危険防止でまずは撤去が先になって、時期的な目安とかもこれでいくとどの辺。
市長
そこは橋桁の部分が落ちて、堰き止めてその大きな被害が起きないようにということをどう防ぐかということは、しっかりと考えて適切に対応していく必要があるというふうに考えております。また決まりましたらお知らせします。宮原さん。
記者(FBS)
すみません、FBSの宮原です。私も日産のことでちょっと追加で伺いたいと思うんですけれども、エスピノーサCEOのほうから「グローバル戦略への重要な拠点」という説明があったということですけれども、この日産にとって、市長としてはその九州、北部九州の位置付けとして強みと言いますか、どういった認識を持たれているか教えてください。
市長
そうですね。やはり九州全体がカーアイランドで、日産の苅田工場自体がボリューム的にも、40万台でしたかね、すごく大きなボリュームを持っていて非常に重要な拠点であるというふうに考えています。しかもそれを、技術を支えてくれる働き手の皆さん、あるいはそれを支える企業群がサプライチェーンの中で存在しているという、もうこういう状況が整えられているというふうに思っています。なので、そういった九州エリアの持つ技術力、それからボリューム的にも非常に大きな意味を持っている、グローバル戦略の中でも大きな核を占めるエリアであるというふうに考えております。それは私たちが、またこのグリーンを中心とした経済戦略、あるいは産業構造をつくっていこうということもまた繋がるところもあると思います。そうした意味で、この九州、そして福岡県っていうのは大事な意味合いを持っているというふうに考えております。これは日産さんも認識をされておられる、当然そう考えています。
記者(FBS)
その上で、その九州エリアのメリット、強み、利便性だったりが認められると、逆に苅田のほうに、九州のほうに集約されてくるっていう可能性もあるのかなと思うんですけれども、日産に対して今後の工場の検討について、何か働きかけなどをする考えについてはいかがでしょう。
市長
そこは私ども、服部知事と私、一緒に並んで九州の持つ、福岡県の持つ重要性、これはお伝えをさせていただきましたし、あらゆるレベルで重要な拠点であるということをお伝えをして、そして経営判断の中でしっかりと考慮していただくように期待をしたいと思います。ただ、これはやはり日産自動車さんの経営に直接関わる話でありますので、もちろんその判断の責任、判断していくというのは会社のほうでありますから、そこはしっかり、私たちとしてはそういうことはお伝えをしながら、しっかりと判断していただくことを期待していきたいというふうに考えています。はいどうぞ。
記者(西日本新聞)
すみません。西日本新聞の井崎です。私もちょっと発表案件以外でよろしくお願いいたします。学校法人明治学園が北九州で初めてとなる小学校授業を英語で行うインターナショナルスクール、インターナショナルコースになるのかもしれませんけど、これを設置に向けて動いております。設置の背景には市の企業誘致、順調な企業誘致に絡んで海外の企業の進出もあることを見据えたものだということなんですが、これ市長の受け止めをよろしくお願いいたします。
市長
そうですね。先日、新理事長と新校長もおいでになられて、明治学園さんの今後の方向性やビジョンについてお話しをいただきました。やはり北九州市が誇る伝統校である明治学園、これが新たな一歩を踏み出すということは敬意を表したいと思います。明治学園さんはこれまでも先進的な英語教育に取り組んでこられたという歴史がある中で、さらにグローバル人材の育成というところに力強い一歩を踏み出そうということは本当に意味が深いと思います。ちなみに私自身の公約の中でも英語教育の強化っていうのは掲げさせていただいておりましたので、そういった方向性というのは一にしているということで大いに歓迎をしたいと思います。今、井崎さんがおっしゃっていただいた企業誘致との関係、これ本当に大きいです。国内外の投資、もちろんもう国内でもそうなんですけれども、やっぱり教育環境というのはものすごく大きなファクターです。そうした中で、やはりインターナショナルな人材をつくっていくような学び舎ができるということはものすごく私たちにとっては大きなアピールポイントになりますので、しっかりとPRをしていきたいというふうに思います。ちなみに海外企業、北九州市の強みに関心を持つ海外企業からの問い合わせっていうのも、いわゆる現地視察っていうのも、これも件数が増加中でございます。その際、やはり質の高い教育を英語で行うということは、やはり大事な要素であって、そこが入ってくるというのは大きな追い風になってくるというふうに思います。従って、このインターナショナルなコースをつくっていくということに関しましては、しっかりとPRをしていきたいというふうに思っています。
記者(西日本新聞)
ありがとうございます。なかなか私立学校というのは県の管轄でもありますし、市として何かできることというのは限られるのかもしれないですけど、何か支援とかすることっていうのは考え得ることでしょうか。
市長
そうですね。もちろん所管という意味からすると県でございますけれども、やはり私たちも密に情報交換をするとともに、あるいはこういう支援制度、補助金などをうまく活用できるんじゃないかというような情報提供であったり、あるいは県との橋渡しというか、そういったことで、できる限りの伴走したペースで、あるいは伴走というものをやっていきたいというふうに考えています。
記者(西日本新聞)
ありがとうございました。
記者(毎日新聞)
毎日の伊藤です。どうもお久しぶりです。これ教育委員会マターのお話で、ちょっと直接市長にとってはあれなんですけれども、門司の松ケ江南小学校に植えてあった11本の桜の木が住民の方に説明なしに全部切られてしまったということがあっています。市長このお話はご存じですか。
市長
報道されましたのでそれは見ております。
記者(毎日新聞)
ざっと言いますと、学校の隣に家が建つことになったので枝が邪魔だというところから始まって、11本のうちに倒れそうで危ないという木も5本ぐらいあったらしいんですね。それもあったのでいっそもう全部切ってしまおうと。校舎の改築工事も控えていてその足場をつくるのに桜が邪魔だということもあったそうで、それなりの理由はあったと思います。学校のほうにもですね。ただやはり一番の問題は、そういったことをどうして事前に住民の方にお知らせしてよりよい方法が考えられなかったのかということだと思います。今回は舞台が学校でしたけれども、例えば樹木に限定して言えば公園ですとか街路樹ですとか、市が管理していらっしゃるところで同じようなことも今後起きる可能性はまたあると思います。市長は今回の事案ご覧になってどういうふうな感想と言いますか、考えをお持ちでしょうか。
市長
行政が何か事業をする時は万事において、しっかりと関わる方々とのコミュニケーション、旦過もそうですし苅田の工場のこともそうですし、やはり様々な情報を集め、そして必要な対話、丁寧に行っていくということは大事なテーマであります。やはりここに向かって、どのテーマであっても、政策分野であっても行政としてそういった取組をしていくことは大事なことだろうというふうに思います。この本件についての詳細な経緯とかどんな説明をしたのかということはちょっとまた、今日は担当来てないですよね、本件についてはね。それはちょっとそちらに聞いていただければと思います。
記者(毎日新聞)
どうもありがとうございます。どうしてこういうことを伺うかって言うと、実はこれYahoo!ニュースにも転載されまして、そこにコメントがもう1000何百通来ているんですね。かなり反響を呼んでいるんですが、見る限りは「もう倒れたら危ないんだからこれを切るのは当たり前だ」とか「そういうことで学校を非難するのは本末転倒だ」といった、住民の方をちょっと責めるようなコメントが非常に多いんですね。さっきも申し上げましたとおり、学校にももちろん理由はあったと思いますが、やっぱりこれをきちんと、もう何十年間愛されてきた木がいきなり切られたら、やっぱり住民の方が嘆くことはやっぱり当たり前だと思いますので、やはり一番の問題はそこの、行政としてもこの説明責任だというふうに私は思いますので、こういった今ネット社会ですので、こういったコメントが広がると地域の方におかしなまたご迷惑なんかかかるようなことにもなりかねませんので、市長もう一度、恐縮ですが先ほどおっしゃった、やはり行政はその説明責任が大事だということをちょっともう一度お答えいただければと思います。
市長
SNSでどういう反応があったっていうところまでは私もちょっとつぶさに把握をしておりませんが、やはりいろいろなテーマについていろんな方がいろんな議論するということは許されていることではありますけれども、やはりそのSNSの使い方、その中での議論の仕方、ここはやはり品位を持ってやっていくということが、どのテーマについても大事だろうというふうに思います。もちろんもうあらゆることにおいて、やはり行政は行政として、住民の皆さんといろんなテーマについてしっかりと今コミュニケーションを取っていくということは行政の1つの大切な要素でありますので、本件についてというわけではなくて、やはりあらゆることについてそういうようなコミュニケーション、今回の件は私もまだちょっと具体的なところまで聞いてないので何ともコメント、ちょっとここではしづらいのでまた後ほどしていただければと思いますが、やはりそういったこと、しっかりとコミュニケーションというのは大事なものだというふうに考えております。
記者(毎日新聞)
はい、ありがとうございました。
担当者(市長公室 報道課)
他質問ございますでしょうか。よろしいですかね。なければこれで定例会見を終了させていただきます。
担当者(都市戦略局 空き家活用推進課)
すみません、空き家活用推進課です。すみません、先ほど「全日不動産協会さんの他都市の指定状況、数どれぐらいありますか」というのがあったんですけれども、4都市で指定されておりましたので、申し訳ないですけど今お知らせします。以上です。
市長
はい、ありがとうございます。
担当者(市長公室 報道課)
すみません、これで定例会見を終了させていただきます。
市長
ありがとうございます。
このページの作成者
市長公室報道課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。