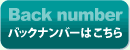【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】
新型コロナウイルス 正しい知識で、正しく防ぐ
Vol.6
問い合わせは北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル 電話0570・093・567
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、一人一人が「うつらない、うつさない」という意識をもって行動することが大切です。皆さんの命と大切な人の命を守るため、本市の新型コロナウイルス感染症対策「5つの行動目標」を実践していきましょう。今回は「発熱等があるときは、事前に電話をしてから病院に行く」について説明します。
北九州市5つの行動目標
1 外出するときはマスクの着用
2 人との距離をしっかり確保
3 小まめに手洗い
4 発症した時のために、自分の行動をしっかりと記録
5 発熱等があるときは、事前に電話をしてから病院に行く
体調が悪いときは外出をしない
発熱など風邪の症状があるときは、学校や会社を休むなど、外出を控えてください。外出を控えることは、自分自身のため、他の人に感染を広げないための大切な行動です。
まずは電話をしてください
発熱などがあるときは、あらかじめ医療機関へ電話でご相談ください。新型コロナウイルスの感染が疑われると判断された場合には、検査を受けることになります。
次のような症状があるときは相談を

□息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠(けんたい)感)、高熱などの強い症状がある人。

□発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状があり、次のいずれかにあてはまる人。
〈重症化しやすい人〉
- ●65歳以上の高齢者
- ●糖尿病や心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある人
- ●透析を受けている人
- ●免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
〈上記以外の人〉
- ●4日以上症状が続く人は必ずご相談ください。(個人差がありますので、強い症状と思う場合や解熱剤などを飲み続けなければならない場合はすぐに相談を)
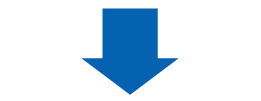
北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル
電話0570・093・567
※聴覚に障害のある人
FAX093・522・8775

かかりつけ医やお近くの医療機関へ必ず電話で相談。
緊急の場合を除いて直接行くことは控えてください。

PCR検査・抗原検査
●中小事業者等(法人・個人)の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税などを軽減します
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(法人・個人)に対して、令和3年度課税分に限り、「事業用家屋」と「償却資産」に係る固定資産税と都市計画税を軽減します。
[対象者]
本市に「事業用家屋」や「償却資産」を所有し、認定経営革新等支援機関等(金融機関や税理士事務所など)から事業収入減少の確認を受けて、来年2月1日(月)までに申告をした法人・個人。
[適用条件]
今年2〜10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額が前年同時期と比べて
30%以上50%未満減少している場合
課税標準が「2分の1」となります。
50%以上減少している場合
課税標準が「ゼロ」となります。
詳細は問い合わせを。市のホームページ(右記を読み取り)でもご覧になれます。
問い合わせは財政局固定資産税課
| ●事業用家屋について | 電話093・582・2036 |
| ●償却資産について | 電話093・582・3210 |
インフルエンザの予防接種を受けましょう
冬に流行する「インフルエンザ」ですが、今年は新型コロナウイルス感染症との同時流行が心配されています。今年度は、高齢者の接種費用が無料になります。また、医療機関や福祉施設、教育機関などに勤務されている人に加え、妊娠されている人、中学3年生相当の人、高校3年生相当の人は自己負担1000円で接種できます。予防接種を希望の人は医療機関にご相談の上、早めに予約し、接種を受けましょう。
問い合わせは各区役所保健福祉課健康相談コーナー
| ●門司区 | 電話093・331・1888 |
| ●小倉北区 | 電話093・582・3440 |
| ●小倉南区 | 電話093・951・4125 |
| ●若松区 | 電話093・761・5327 |
| ●八幡東区 | 電話093・671・6881 |
| ●八幡西区 | 電話093・642・1444 |
| ●戸畑区 | 電話093・871・2331 |
市の担当課 保健福祉局感染症医療政策課 電話093・582・2430
11月は児童虐待防止推進月間です
「しつけ」と称した「体罰」がエスカレートした結果、重大な児童虐待事件を引き起こす痛ましいニュースが後を絶ちません。
本市では、市民一丸となって、児童虐待のない子どもの安全と健やかな成長が守られる社会をつくるために、「北九州市子どもを虐待から守る条例」を施行しました。
令和2年4月から、子どもへの体罰は法律で禁止されています。子どもの権利を守り、体罰などによらない子育てを広げ、虐待のない社会を実現していきましょう。
「しつけ」と「体罰」の違い
「しつけ」とは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。
たとえ「しつけ」のためだと保護者が思っても、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こしたり、不快感を意図的にもたらす行為は、どんなに軽いものであっても「体罰」です。

![]() 体罰の具体例
体罰の具体例
●何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
●いたずらをしたので、長時間正座させた
●宿題をしなかったので夕食を与えなかった
体罰以外にも、衣食住の世話をしないなど保護の怠慢や拒否(ネグレクト)、著しい暴言は虐待として禁止されています。また、子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動も子どもの心を傷つける行為で、子どもの権利を侵害します。

なぜ、「体罰」などをしてはいけないのか
体罰などが繰り返されると、子どもの心身の成長・発達にさまざまな悪影響を及ぼす可能性が、科学的にも明らかになっています。
「体罰」などによらない子育てとは
(1)子どもとの関わり方の工夫
●子どもの気持ちや考えに耳を傾ける
●子どもが言うことを聞かない理由を考えてみる
●肯定文でわかりやすく伝え、時には保護者自身が手本となる
●良いこと、できていることを具体的に褒める など
(2)保護者自身の工夫
●ストレスや否定的な感情に気付き、認め、原因を振り返る。
●深呼吸をしたり、ゆっくりと5秒数えたり、窓を開けて風に当たったりして気持ちを落ち着かせ、気分転換をする。時には、保護者自身が休む。
●上手くいかないときは、周囲の力を借りると解決することも。勇気を出して、SOSを出す。

子育ては、いろいろな人の力と共に
子育てを頑張るのは、とても大変なことです。保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、まずは、お住まいの区役所保健福祉課「子ども・家庭相談」コーナーに相談を。
虐待かもと思ったら
![]()
児童相談所虐待対応ダイヤル(通話料無料)※匿名でも構いません。
児童虐待問題連続講座
11月30日(月)13時30分~16時30分、戸畑市民会館(戸畑駅前、ウェルとばた3階)で。定員、定数 先着300人。手話通訳・要約筆記あり。
- [講座内容]
- 「児童福祉法等の改正による体罰の禁止について」=講師は、子ども家庭局子育て支援課主幹・江副久美子。
- 「過去は取り戻せるのか〜逆境的小児期体験の科学」=講師は、八幡病院統括部長・小児総合医療センター長・神薗淳司。
- 「子どもの心の声を聴く〜子どもアドボカシー入門」=講師は、熊本学園大学教授・堀正嗣さん。
申し込みは11月4日から問い合わせ先へ。聴覚障害者はFAXも可。
問い合わせは北九州市社会福祉研修所 電話093・873・7655 FAX電話093・873・7656
市の担当課 子ども家庭局子育て支援課 電話093・582・2410
若者ワークプラザの新しい就活支援メニューの活用を

若者ワークプラザ北九州は、コロナ禍における就職活動への支援メニューを充実させ、利用しやすいよう相談時間も延長しています。
支援メニュー例
●WEB面接用の機材の貸し出しや場所の提供
●求職者向けWEB面接セミナーの開催
●就職氷河期世代就業支援
●伴走型の正社員就職支援
●「フォークリフト免許」など、資格取得支援の拡充
若者ワークプラザの講座
(1)WEB面接(実践編)
面接時の注意点やビデオ会議アプリ「Zoom」の利用方法など。11月7日(土)13~15時、若者ワークプラザ北九州で。定員、定数 4人。
(2)なるほど!労働法と社会保険「働く上での基本ルール」
11月13日(金)10時15分~12時、若者ワークプラザ北九州・黒崎で。定員、定数 12人。
共通の内容 対象 おおむね40歳までの求職者・学生。申し込みは電話で各開催日の前日までに(1)は若者ワークプラザ北九州、(2)は若者ワークプラザ北九州・黒崎へ。
問い合わせは若者ワークプラザ北九州(小倉駅北側、AIMビル2階)電話093・531・4510
月〜土曜日(祝・休日、年末年始は除く)の10〜18時(予約制で月〜土曜日の18〜19時と第1・3日曜日の11〜15時も開館)
問い合わせは若者ワークプラザ北九州・黒崎(黒崎駅西側、コムシティ2階)電話093・631・0020
月〜土曜日(祝・休日、年末年始は除く)の10〜19時(予約制で第4日曜日の11〜15時も開館)
「働き方改革」進んでいますか?
昨年4月から「働き方改革に関する法律」が順次施行されています。改革の大きなポイントは次の3点です。
時間外労働の上限を規制 昨年4月1日施行(中小企業は今年4月1日から)。時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得 昨年4月1日施行。使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止 今年4月1日施行(中小企業は来年4月1日から)。同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
働き方改革についての相談窓口(事業者向け)
問い合わせは福岡働き方改革推進支援センター フリーダイヤル0800・888・1699
市の担当課 産業経済局雇用政策課 電話093・582・2419