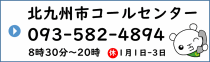火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、全国一斉に11月9日から11月15日の一週間を、重点的に火災予防啓発を行う期間としています。市民や事業所等の火災予防思想の普及と高揚を図ることで火災の発生を予防し、高齢者や障害者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施します。
令和7年秋の火災予防運動

令和7年秋の火災予防運動のチラシ(表面)(PDF形式:1.5MB)
令和7年秋の火災予防運動のチラシ(裏面)(PDF形式:532KB)
令和7年秋の火災予防運動
1 令和7年度全国統一防火標語
『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』
2 実施期間
令和7年11月9日(日曜日)から11月15日(土曜日)まで
3 重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(3)地震火災対策の推進
(8)放火火災防止対策の推進
令和6年中の北九州市内における火災状況
| 項目 | 火災状況 | 令和5年との比較 |
|---|---|---|
|
火災件数 |
220件 |
23件増加 |
|
死者数 |
17人(うち高齢者12人) |
7人増加(うち高齢者2人増加) |
|
住宅火災による死者数 |
14人(うち高齢者9人) |
8人増加(うち高齢者3人増加) |
|
負傷者数 |
33人 |
3人増加 |
|
損害額 |
約8億3千万円 |
約6億6千万円増加 |
| 順位 | 原因 | 件数 |
|---|---|---|
| 1位 | たばこ | 32件 |
| 2位 | 放火(疑い含む) | 24件 |
| 3位 | 電灯・電話等の配線 | 20件 |
| 4位 | こんろ | 17件 |
| 5位 | 電気機器 | 16件 |
火災予防のための具体的な取組み

住宅防止 いのちを守る10のポイント
4つの習慣
(1)寝たばこは絶対にしない、させない。
(2)ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
(3)こんろを使うときは火のそばを離れない。
(4)コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
(1)火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
(2)火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
(3)火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
(4)火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
(5)お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
(6)防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
- 動画投稿サイトYouTube 【公式】北九州市消防局
- 【YouTube】住宅用火災警報器の鳴動状況(外部リンク)
- 【YouTube】「無線式連動型」住宅用火災警報器の鳴動状況(外部リンク)
令和7年秋の火災予防運動における主要行事(予定)
秋の火災予防運動メインイベント
本気予防(ガチ ヨボー)
日時
令和7年11月15日(土曜日)10時から15時
場所
小倉北区魚町1丁目4番16号 魚町みらい広場(鳥町食道街跡地)
内容
詳細は「秋の火災予防イベントを実施します!」ページをご覧ください。
各区での火災予防イベント
| 行政区 | 実施日 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 門司区 | 10月25日 | 栄町銀天街 | 栄町銀天街での予防広報 |
| 小倉北区 | 期間中随時 | JR小倉駅新幹線改札口 | デジタルサイネージでの広報 |
| 小倉南区 |
11月2日、8日、16日 |
区内4校区 |
防災訓練等(消火器取扱訓練、煙体験等) |
| 若松区 | 11月6日 | 大黒市場・共栄市場等 | みんなの市場・地域ぐるみにおける防火啓発及び広報 |
| 八幡東区 | 期間中随時 | 区内各所 | まつり起業祭や物品販売店等での広報 |
| 八幡西区 | 11月7日 | 熊手市場 | 市場商店街消防演習 |
| 戸畑区 | 11月14日 | 中本町アーケード中央広場 | サポ笛を活用した消防活動訓練 |
各区でのイベントについては詳細が決まり次第随時更新します。
| 消防署 | 電話番号 |
|---|---|
| 門司消防署 | 093-372-0119 |
| 小倉北消防署 | 093-582-0119 |
| 小倉南消防署 | 093-951-0119 |
| 若松消防署 | 093-752-0119 |
| 八幡東消防署 | 093-663-0119 |
| 八幡西消防署 | 093-622-0119 |
| 戸畑消防署 | 093-861-0119 |
| 消防局予防課 | 093-582-3836 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
消防局予防部予防課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3836 FAX:093-592-6795
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。